【結論】夜泣き対応で一番大切なのは“完璧を目指さないこと”
育児をする上で、ほぼ全てに人が経験するであろう「我が子の夜泣き」。明日仕事で朝が早かろうが容赦無く降りかかるこの現実に、誰もが心身ともに悩まされますよね。少しでもこの苦しい現状を打破したいパパさんは多いのではないでしょうか?
結論からお伝えすると、夜泣き対応で一番大切なのは「完璧を目指さないこと」です。
「毎回ちゃんと対応しないと」「妻に任せっぱなしはダメだ」と思いすぎると、パパ自身がどんどん追い詰められてしまいます。
「夜泣きは一時的なもの。」私自身も先輩パパさんにアドバイスされて救われた一言です。
手を抜けるところは抜き、頼れるところには頼って、自分の心身を守ることが長い育児生活では何より重要なのです。
寝不足で限界…夜泣きがパパに与えるダメージとは?
1. 睡眠不足による集中力低下とイライラ
夜泣きで起こされると、慢性的な睡眠不足に。眠りが深い時ほど、きついですよね・・・。やはり睡眠は健やかな生活を送る上で必須な時間です。
寝不足により仕事中もぼーっとしたり、普段なら気にならない些細なことでもイライラしたりしてしまいます。
2. 心の余裕がなくなり、パートナーとの関係も悪化
働くパパの身としては、仕事と育児の両立に疲れ果て、何かと行き届かないことが起こりがちに。我が家もちょっとしたことが原因で、夫婦げんかに発展することもしばしばありました。奥さんと揉めると家での居心地も悪くなり、悪循環が加速します・・・。
「自分ばかり大変」とか「なんで俺ばっかり・・・」と感じやすくなり、ストレスがさらに蓄積してしまいす。
3. 自己嫌悪に陥りやすい
「ママじゃないと泣き止まない」「もっとちゃんと対応しなきゃ」「怒っちゃってダメだったな」と、うまくできない自分を責めがちに。奥さんにも気を遣い、子どもにも当たってしまたりと、思い通りに行かない現実に途方に暮れるものです。当時の私もこの状態に陥っており、今思えば暗黒時代でしたw。
でも、誰だってつらいんです!まずはその事実を認めてあげましょう。
パパでもできる!夜泣き対策の基本ステップ
1. 泣いてもすぐ焦らず一呼吸
夜泣きが始まると、すぐに抱っこしてあやしにかかりがちです。私も毎度全力であやしにかかってましたが、結局自体が悪化したり、終わりの見えないマラソンファイトに突入して余計に消耗したり・・・そんな日々でした。そしてそれを見かねて結局奥さんが抱っこするというパターンに。もう自己嫌悪が止まりませんw。
夜泣きには波があります。
すぐに抱き上げず、少し様子を見るだけでも自然に落ち着くことがありますし、深呼吸して気持ちを整えるのも大切です。
2. 子どもの環境を整える
夜泣きの原因にはいろいろパターンがありますが、まずはおむつの状態、寝室の温度や湿度、明るさ、音など、赤ちゃんが安心できる環境かをチェック。
案外、ほんの少しの違いが夜泣きに影響していることもあります。
うちの子は夜風に当たると落ち着くことが多かったです。季節や天候にもよりますが、思いきった変化が赤ちゃんにハマるケースもあります!
3. 自分にしかできない対応を探す
パパならではの抱っこやトントン、おんぶや肩車など、ママにはないアプローチの方法を見つけると自信にもつながります。思いつく限り、手当たりしだい試してみましょう!
リアルに効果があった!夜泣き対応の乗り切り方5選
① 交代制を取り入れる
我が家では平日はママ・土日はパパというように、夜泣きや深夜のミルク対応をメインで行う役割を交代制にしていました。
少しでも優先的に眠れる日を確保できると、心と体がリセットされます。
② 夜泣き専用アイテムを活用
ホワイトノイズマシンやメルシーポット、赤ちゃん用のアロマスプレーなど、夜泣き緩和グッズが意外と助けに。
便利グッズは積極的に試してみるのもおすすめです。
もはや都市伝説的なネタですが、私の周りでは反町隆史さんの「POISON~言いたいことも言えないこんな世の中は~」のイントロが効くと話題でした♩
③ 寝かしつけ前のルーティンを作る
「絵本を読む→暗くする→音楽をかける」など、同じ流れを毎晩続けると、赤ちゃんも安心しやすくなります。
我が家のルーティンは「寝室に行く前に思いっきりコチョコチョをする→寝室を暗くする→スマホでヒーリング系の音楽を小音で流す」を実践していました(今もほぼこのルーティン継続中)。
ちなみに音楽は細胞修復や睡眠効率が上がると言われている528hzの周波数のものを選んでいます。YouTubeやAmazon musicで無料で活用できます!
④ 抱っこひもを使って“ながら対応”
寝かしつけのときは抱っこひもを使うのも有効です。
手が空くので何かをしながらあやすこともできます。やり残した家事をやったり、音楽を聴く・家の中や外を歩くなど、自分のストレス軽減も兼ねて気を紛らわしましょう。
⑤ 開き直って「今日は寝かせてもらいます」宣言
どうしても無理な日は、正直に「今日は無理です」と奥さん伝えてみましょう。
無理しても誰も得しません。さらに体を壊しても本末転倒です。
休む勇気も、育児には大切です。もちろん奥さんが開き直る日も受け入れましょう!
ちなみに我が家はこのパターン多かったです。先に言ったもん勝ち的な要素も強かったですが・・・w
ワンオペにならないために…夫婦でできる夜泣き対策の工夫
1. 「一緒にやってる」という感覚を共有する
夜泣きに限らず、「どちらかが全部(大半)やってる」ではなく、「一緒に頑張ってるよね」という感覚があるだけで精神的にラクになります。前提として夫婦間のコミュニケーションがとれているのが理想ですね!
2. 夫婦でルールを作る
「起きるのは交代制」「日曜はパパが朝寝坊OK」など、お互いにとってフェアなルールがあると不満が減ります。大変なことは持ちつ持たれつで!
我が家の場合、特殊ルールがありまして、双方やりたくないモードの時は正々堂々「じゃんけん」で決める時がありますw。恨みっこなし、ゲーム感覚で育児や家事を乗りこなす奥の手です!
3. 不満をためない“週1ミーティング”
夫婦で毎週数分話す時間を作り、ストレスや気になることを話せる場を。
不満をためこまない仕組みは、夜泣き対策よりも大事かもしれません。
まとめ:頑張りすぎない夜泣き対応で、パパも心に余裕を
正直、夜泣き対応に正解はありません。
でも、「完璧じゃなくていい」「ひとりで抱えなくていい」ということを忘れずにいてください。
つらい時期ではありますが、子どもが成長すれば夜泣きの時期は確実に終わるものです。
今は“ほどよく手を抜きながら”、家族で一緒に乗り越えていきましょう。
このブログ「パパ育LOG」では、働くパパたちのリアルな悩みに寄り添う情報をこれからも発信していきます。
あなたの育児が、少しでも楽になるヒントになりますように。

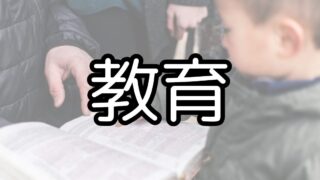
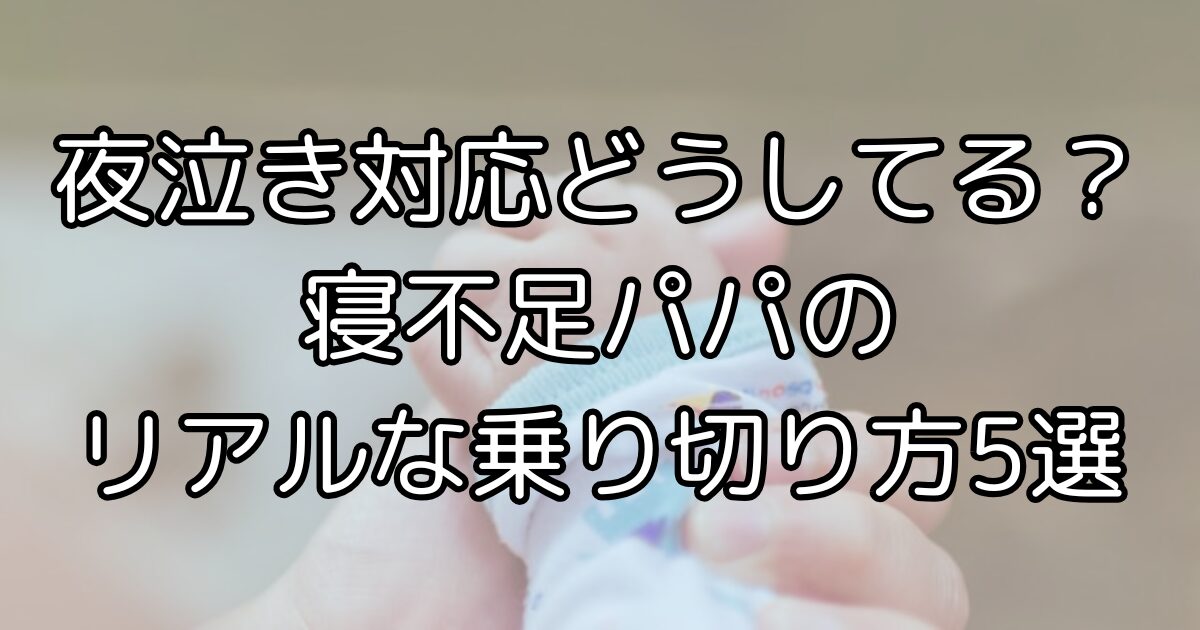
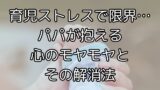


コメント