【結論】叱らずに接するには、「子どもの気持ちを代弁」→「選択肢を提示」→「認める」ステップがおすすめ
何を話しかけても頼み事をしても「イヤ!」。育児を経験する上で避けては通れない我が子の「イヤイヤ期」。イヤイヤ期に突入した子どもが「イヤ!」を連発し、ついイライラしてしまうパパさん、すごく気持ちわかります・・・。
この記事ではそんな「イヤイヤ期」に悩むぱぱさんへ向け、叱らずに接する実用的な“言葉がけステップ”をご紹介します。 これを読めば、「どう声をかければイヤイヤが和らぐか」「イライラを減らして笑顔で向き合えるか」がわかります。私のリアルな経験談も踏まえ、ぜひご参考ください!
イヤイヤ期とは?パパが知っておくべき子どもの心理背景
そもそもイヤイヤ期とは、子どもが成長する過程で自己主張がとても強くなる時期のことをいい、一般的に1歳半〜2歳前後だと言われています。パパやママからの声かけに対し、自分の意にそぐわない事は「イヤ!」と拒絶するため、イヤイヤ期と呼ばれるようになったそうです。
① 自我の芽生えで「自分」を主張し始める
親にとっては嬉しいようで複雑な心情になる子どもの成長と自我の目覚め。2〜3歳の子どもが「イヤ!」と言い始めるのはごく自然な事で、順調に発達している証拠です。子ども本人にとっても自我を育てようとする大事な時期なんですね。
② 言葉より感情が先に出る時期
この頃の子どもは、自分に掛けられている言葉の意味が概ね理解できているが、どう返していいかの選択肢やバリエーションが乏しい時期です。頭で考えて返すより、好き・嫌いといった感情や気持ちが先行しやすいのが特徴です。いわば条件反射のように、リアクションを“言葉”として表現できず、行動で示してしまいやすいんです。
③ 試している・自分でやりたい気持ちの表れ
子どもにとってもやりたい事と自分の能力が上がってきてリンクしてき始める時期でもあります。思った通りに物事が進むことが嬉しくて、言わばなんでもチャレンジしたくなるお年頃です。自分のできる範囲を試したいという欲求が高まるので、それが阻害されるかもと感じると「イヤ!」と反発しますが、これはれっきとした成長の一環でもあります。
我が家のイヤイヤ期の状況
私の娘が「イヤイヤ期」に突入したな!?と確信したのは、ちょうど2歳1ヶ月くらいの時期でした。この頃から「自分でやりたい」感が強まってきており、何かに夢中になるとどれだけ時間が経っても、何を言っても辞めようとしなくなることが増えてきました。

自宅ではもちろんのこと、お出かけ先でもお構いなくイヤイヤぶりとマイペースを発揮していました。「100歩譲って家で癇癪起こすのは許容できるが、出先では勘弁してくれ・・・」。これは皆さんあるあるな心情ではないでしょうか?

せっかくの気合いを入れたお出かけや旅行先でもこの有様・・・。周りの皆様への迷惑も顧みず、大声で全身アクションで「イヤイヤ」する姿は、さすがの愛娘でもイライラしてしまいます。当時の私は、外でのこの現象が本当に苦手でした。本音としては近所のスーパーやドラッグストアに連れて行くだけでも嫌だなと思ってしまうほどでした。
「いつまでこの感じが続くんだ・・・?」と、かなり精神的にもまいってしまっていて、モヤモヤとイライラを募らせる日々でした。
そんな時に先輩パパさんからアドバイスいただいた内容が、当時の私を大きく救ってくれたのです!
嫌がる子どもを叱らない声かけ3ステップ
3人の育児をされた先輩パパさんから、私が実際にいただいたアドバイスをご紹介します。
1. 気持ちを代弁する:「〜したかったんだね?」
子どもが「イヤイヤ」しているということは、その裏側の心理として「何かをしたい」が潜んでいます。例えば椅子に座りたがらない子どもとのシュチュエーションだと、

座りなさい!

いやや!!
と、こんな感じのやり取りの繰り返しになりますよね。この時の子どもの心理には、「歩きたい、動きたい、あっちへ行きたい」というような座るとは別の“やりたい”が潜んでいます。
この心理を読み取ったり予測して、あえてそれを言葉にしてあげることが効果的です。

歩きたかったんだね?

・・・うん。
こんな感じで、「自分を分かってもらえた」と安心し、大きな反発が軽減されます。これは実際うちの娘にも効果抜群で、大きな癇癪をかわす貴重なノウハウでした!
2. 選択肢を与える:「どっちがいい?」
自我を発揮した時の子どもは一点集中して目的に向かいます。その時この時期の子どもはおそらく他の選択肢を思いつかないほど「今したい事」に一直線です。そんな時は子どもに選択肢を与えてあげましょう。
▪️「絵本を弟に貸してあげて?」に対し「いやや!」とぐずった時の例

絵本を読むか積み木で遊ぶか、どっちがいい?

・・・積み木にする!
と言った具合に、本人の中になかった選択肢が提示されると一瞬我に返り、今したいことを再選択する時間が生まれます。私の経験上、あくまで選択肢の一つは本人の自我でしたいことを入れるのがポイントです。二つとも自分の意思に沿ってないものを提示されても、余計反発するパターンが何度もありました。
こういった選択と意思決定は、自分で考える機会になるだけでなく、親から言われるのを押し付けられるのでもなく、自分自身で選んだという安心感が生まれます。
3. 小さな成功を認める:「〜できたね、すごい!」
どんな些細なことでも、その時できたことややりきったことに対して褒めて承認するというアクションも大切です。「イヤイヤ」モードを発動してぐずっていても、子どもの根幹にあるのは「拒否」ではなく「承認」です。その都度イライラしてしまいがちですが、親の私たちがグッと堪えてこのアクションを意識的に行うことが大切です!

絵本、貸してあげたんだね!えらいね!さすが〇〇ちゃんだね!

わたしお姉ちゃんだもん!
こんな感じで、子どもの自信や次の挑戦意欲を育てるアクションになります。大人でもそうですが、やはり褒めて伸ばすというのは効果的ですね!
パパが実践する時のポイント
先輩パパから教わったアドバイスを、さらに効果的に行うポイントが3つあります。
- 声のトーンは穏やかに:高圧的ではなく、安心感のあるトーンへ意識しましょう。
- タイミングは短く簡潔に:子どもの聞く集中力が続かないので1〜2文で簡潔に伝える。
- 表情・アイコンタクトを忘れずに:言葉以上に「気持ち」が伝わります。しっかり目を合わせて笑顔や真剣な顔を言葉の内容に合わせて使い分けましょう。
これはできたらさらに効果的という内容なので、まずは「気持ちを代弁する」「選択肢を与える」「小さな成功を褒める」の3つを確実に行うこと優先して意識していきましょう!
実例!こんな時どうする⁉︎ リアル体験談3選
当時意識的に実践して効果を感じたシュチュエーションでの、娘と私のやりとりをご紹介します。
① おもちゃで散らかったリビングでお片付けイヤイヤ

お片付けして!

いやや!

じゃぁ、お片付けできたらお散歩行こうか!
パパと一緒にお片付けする?それとも自分でお片付けする?

・・・パパとする!
選択肢&未来の楽しいシーンを想像させることで、子どもがモードチェンジ!お片付けのやる気が生まれました。
② 保育園の登園時間間際での着替えイヤイヤ

時間ないんだから、早く着替えて!!

いやや!!

この花柄の服着たら〇〇ちゃんもっとかわいいよ〜⁉︎それともこっちのパンダのTシャツにする⁉︎

・・・パンダにする!
選択肢を与えられるとスムーズに受け入れ、あっさり服を着てくれ私も笑顔で家を出られました。
③ お腹空いてるのになかなか食べ進まないご飯イヤイヤ

ご飯食べないならもう下げちゃうよ⁉︎

いやや!まだ食べる!

そっか、まだ食べたいんだね⁉︎
ならスプーンで食べる?それともフォークで食べる?上手に食べれたら、デザートにバナナもあるよ?

スプーンで食べる!バナナもちょうだい!

お、上手に食べれたね!!すごいじゃん!
きれいに食べれたからデザートのバナナね、はいどうぞ!
こんな感じで気持ちを代弁→選択肢提示→成功の言葉がけで、完食へつながりました。あんなにごねてたのが嘘のように、バナナまでペロっと食べてしまいました😂
パパが陥りやすいNG対応パターン
私が先輩パパさんにアドバイスをもらう前に取り入っていた、よくあるNGパターンをご紹介します。思い当たるものがないか、ご自身と照らし合わせてみてください。
× 長々説教モード
子どもに対して「わかって欲しくて」「ちゃんと理解して欲しくて」と言った思いが先行し、ダラダラとお説教のように説いてしまうパターンです。伝える時間も長く要点もボケやすいので、結果パパは何が言いたいのか子どもにも理解できない状況になりがちです。
大人もダラダラ説教されるとうんざりしてしまうのと同じで、子どもにもとってもこの時間は大きなストレスになります。反発心が増す上に、気持ちが離れてしまいます。
× 怒鳴りや威圧的な声かけ
「イヤイヤ」モードの時間は親の私たちにとってもイライラが募る忍耐の時間。耐えきれず、つい感情的になって怒鳴ってしまったり威圧的な言葉になってしまったり・・・。当然子どもにとってもよくない結果になりやすく、萎縮や反発につながり親子関係が悪化しやすいので要注意です。
こちらも人間ですから、感情コントロールって難しいですよね・・・。

私もいまだにやってしまいがちです。その後の自己嫌悪感と言ったらありません。まだまだ未熟者です・・・
× 無視や放置
親子ともどもヒートアップしてしまうと収拾がつかなくなるからと、少し距離をおいてクールダウンしようとしたり、冷たく突き放すように距離を取るのもやってしまいがちです。
「一旦冷静になろう」や「ほっとけばいいや」という対応は、子どもが見放されたと感じるリスクがあります。「イヤイヤ」の深層心理には親の注意引くという意図があったりします。それなのにパパたちに無視や放置されると、最悪心のトラウマになってしまうリスクもあります。

この3つのNGパターンは、意識的にしないようにできると理想的ですね!
まとめ:イヤイヤ期はチャンス!パパの声かけを通して心を育てよう
イヤイヤ期は子どもの成長につながる大切な時期。パパが“叱らずに意味のある言葉かけ”を意識することで、子どもの自我を尊重し、笑顔で向き合える時間になります。
押さえるべきポイントは、は「気持ちを代弁する」「選択肢を与える」「小さな成功を褒める」の3つのアクション。小さな変化でも続けることで、毎日がより充実し、家族の関係がもっともっと深まります。子どもの「イヤイヤ期」を通して、子どもだけでなく我々パパも成長していきたいものです!
本ブログ「パパ育LOG」では、育児中のパパに役立つ等身大でリアルな情報を発信しています。次回もお楽しみに!

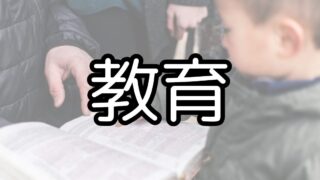
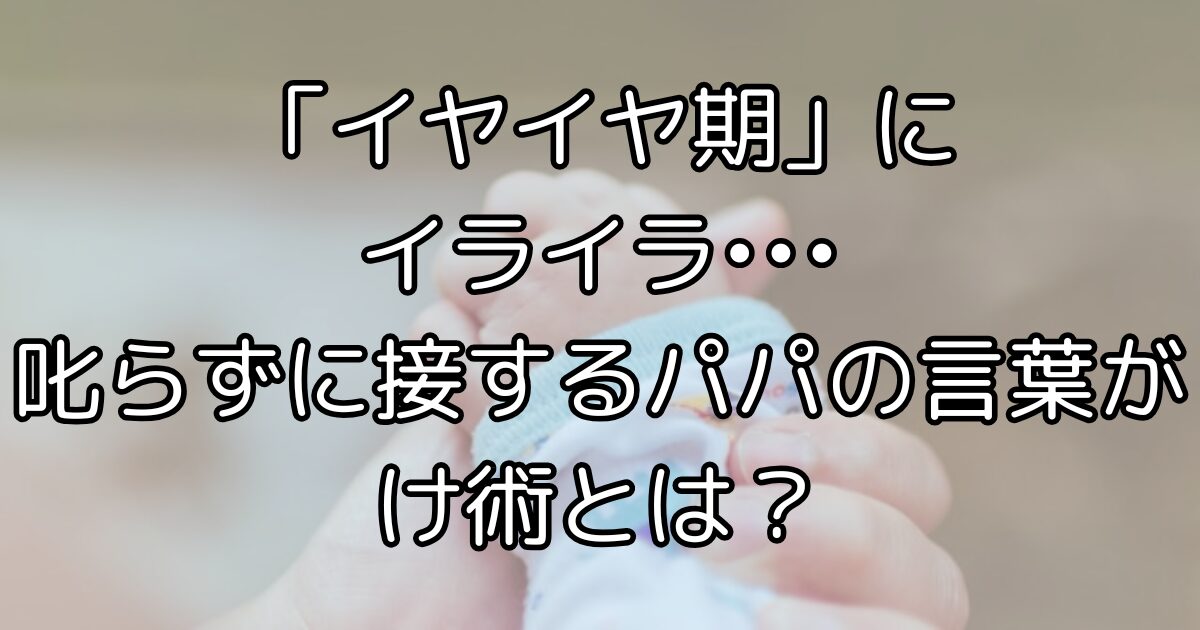
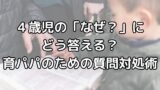
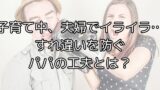
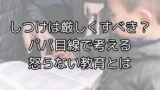


コメント