【結論】「期限」「時間帯」「代替案」の3つでルール化すれば、スマホ依存を防ぎ楽しく親子時間が増える!
「子どもがスマホやタブレットを見たがって困っている…」そんな悩みを持つパパさん多いのではないでしょうか。この記事では、スマホやタブレットばかり見たがるお子さんを持つ30〜40代パパが無理なく実践できる家庭ルールの立て方と具体的な対策をご紹介します。
これを読めば、子どもさんの画面時間を自然にコントロールでき、結果として親子のコミュニケーションも増やすことができます。ぜひ最後までご一読ください!
なぜ子どもがスマホ・タブレット依存になってしまうのか
スマホやタブレットが生活に欠かせない一部になった現代、子どもがその存在を避け続けることはほぼ不可能な時代です。とはいえ、なぜ子どもたちはわかりやすくスマホ・タブレット依存になりやすいのでしょうか?
① 視覚的刺激が強すぎる
そもそもスマホやタブレットは視覚・聴覚・触覚に対し直感的に動作するという性質を持ちます。動画やアプリは視覚・聴覚的に刺激が特に強く、子どもが夢中になる構造になっているんです。
日々全身でインプットを繰り返し成長する幼少期は、「見ているだけで楽しい」という体験が心を掴みやすくみるみるのめり込んでしまうのです。
② 親が忙しいと“お守り代わり”になりがちに
仕事や家事で忙しいとき、つい「ちょっとだけ見てて」とスマホやタブレットを渡してしまいがち。これが手っ取り早く子どもの注意を引き、親の自由な時間をコントロールできるので筆者もよくやってしまっていました。
「今だけ・・・」「少しの時間だけなら・・・」というつもりで渡したスマホが、依存の第一歩になってしまうことも。親の私たちにとっては都合のいいツールですが、子どもに対するリスクも認識しておかなくてはいけなせん。
③ 親が悪い見本になってしまう「ながら視聴」習慣
家族の時間でありがちなシーンとして、パパやママ自身が食事中にスマホを見ることもあるかと思います。「ちょっと天気予報を・・・」「ニュースやSNSをチェック」など、何気なく触ってしまう親のスマホ習慣を子どもはしっかり見ています。親の行動の影響力は意外と強力です。良くも悪くも子どもにとって親の言動は見本であり一番の影響を受ける対象です。
スマホやタブレットの付き合い方は、子どもの価値観と習慣に直結してしまうんです。
ルール化の3ステップで自然に「画面時間」を減らす
時代的に子どものスマホやタブレットを完全に遮断できない以上、どう付き合うかが考え方として大切になってきます。子どもがスマホとうまく付き合っていくためのルール化ができているとやりやすいです。
① 「期限」を明確に決める(例:平日30分、週末60分)
親の都合とはいえ、時にスマホやタブレットは利点も大きいです。それをうまく利用しつつ依存させない環境を作るには、まずスマホを見せる時間を具体的に決めることが重要です。
ポイントなのは、スマホを渡す前にあらかじめ子どもと「今日は30分見ていいよ」「この動画は20分のお約束で見ようね」など、子ども本人と具体的な時間を共有して決めることです。事前に取り決めや条件が揃っていることで、子ども自身も時間になった時自分から使うのをやめたりするようになります。
我が家の娘も、この方法で一回に見れる時間は15分までという我が家の基本ルールがあるので、意外にもすんなり止めます。幸い、彼女の価値観としてスマホを見る欲求<お約束を守ることという比重で行動できているようです。
もしまだ時間の概念がない年齢の時は、タイマーなどを一緒にセットして「これが鳴ったらおしまいね」といった感じで行うと効果的です!
② 「使用時間帯」をルール化(食事中・寝る前はNG)
いつでもどこでもスマホが触れるというのではなく、時間帯や状況を限定してルール化することも大切です。我が家の場合、「筆者が仕事で不在かつママが夕食を作る時間はタブレットを触れる」というお約束になっています。もちろんその時間帯でも本人がタブレットを見たいといえば時間を決めて渡すといった具合に、絶対見せるわけではありません。このタイミングはご家庭ごとで変わってくるので、使用時間帯を設けるならいつがいいか決めていけるといいですね。このお約束が定着してくると、子ども本人の中でもルーティン化して分別がつくようになってきます。
余談ではありますが、スマホやタブレット画面のブルーライトが寝かしつけにや睡眠効率などに悪影響を与えることが知られています。子どもの健康や安全を踏まえた時間帯設定が理想的です。
③ 「代替案」を用意して誘導する
使用する時タイミングや時間のお約束が守れなかった場合や、どうしても駄々をこねる場合は「代わりにこれやってみようか?」と声をかけて代替案を提案してみましょう。もしかしたらスマホやタブレットの方に興味が強くて誘導や切り替えがうまくいかないケースもありますが、有効なのは「パパと一緒に〇〇しない?」と一緒に何かしようという表現がおすすめです。
我が家の娘の場合、このパターンが効果てきめんで「ブロック遊び」「お絵かき」「外遊び」「絵本を読む」など他の遊びへの誘導がうまくいきやすいです。
具体的な家庭ルールの作り方&例
ルール作りのポイント
家庭でのルールを作っていく上で、以下のようなポイントを押さえるのがおすすめです。
- 親子で話し合って決める(子どもとの協調感が生まれる、自分の意思で決めたことで守る意識が増す)
- 見える化する(ホワイトボード・カレンダーなどに記録をためていく)
- ご褒美&記録(ルールを守ったらシールやスタンプで達成感を助長する、シールノートなどが有効)
家庭ルール例

我が家での実際に娘と決めて実践しているルールをご紹介します。
・平日は1日30分まで、週末は60分まで。
・“食事中・寝る1時間前”はスマホ・タブレット・テレビは見ない。
・夕食の準備中の時間に見ることができる。
・ルールを守れなかった時は、おやつの量が減る
・お約束がちゃんと守れたら、シールノートにご褒美シールを貼っていく。
このような感じでルール化しています。守れない時にどうなるかも本人と決めておくと、より守ろうとする力が効果的に働きます。
ルールがうまく機能するための5つの工夫
子どもと一緒にルールを決めただけでは意味がありません。そのルールをより意味のあるものにしていくためのポイントと工夫をご紹介します。
① ルールの「お約束」をパパ自身が守る
子どもがルールを意識したり守っていく上で1番大切な要素として、「お約束」をパパ自身が必ず守っていることが挙げられます。「パパも守ってないなら私もいいや」となってしまいます。この心理状態は、子どもに限らず大人も感じますよね。
親が見本になることで、子どもの理解と実行率が大きく向上します!
② 感情が荒れてきたら「代替遊びタイム」へ誘導
「お約束」が守れなさそうだったり、自我を出してスマホを見続けようとする時は、タイミングを見て声をかけ「お絵かきならどう?」などやわらかく誘導することで反発が少なくなります。子どもの感情が荒れ始めたタイミングで、つい「だめ!」「お約束でしょ!?」のような声かけをしてしまうと、かえって逆効果になることが多いです。
③ お約束が守れた時は“一緒に褒め合う習慣”
親子で決めたルールやお約束をちゃんと守れた時は、「ルール守れたね」「すごい!さすがだね!」などポジティブな声かで承認を積極的にしましょう。子どもは褒められることで、自己肯定感が高まりますし、また褒められたいという感情も芽生えるのでお約束を次も守ろうとします。〇〇できたら褒めてもらえるという行動のルーティン化が起きるんですね!
④ ルールが変化してもOK!家族で振り返る
一度決めたルールやお約束は、状況によって柔軟に変更していきましょう。TPOや子どもの成長度合いによって、「時間延長」「週末だけにする」などルール更新も有効です。
頑なに守るというのも大切ですが、状況に対して柔軟な適応力をつけさせる意味でも、適切なルール変更は良いことです。ただし、基本方針はぶれないようにすることが大切です。
パパ自身が気をつけたい“ながらスマホ習慣”
先ほどご紹介した「パパ自身もお約束を守ろう」につながる話ですが、日頃のパパのスマホ・タブレットの扱い方も大切な要素です。
① 食事中・会話中のスマホはやめよう
食事中や会話中のスマホ使用は家族の大切な時間を奪います。よほどの急用は除き、まずは“食卓タイム”だけでもスマホオフを徹底するのがおすすめです。将来的に子どもがスマホを持つようになった時、この習慣が大きく響いてきます。
② 寝室にスマホを持ち込まない
使わなくてもスマホを寝室に持ち込むのはできる限り避けましょう。子どもたちの寝つきや睡眠効率が低下してしまう可能性があります。また、着信などがあると、寝に入っていた子どもの注意をスマホに向ける結果になってしまいます。
アラーム機能の兼ね合いもありますが、寝室外で充電・管理するだけで生活リズムは確実に安定します。
③ 自分のリセットタイムはちゃんと確保
とはいえ子どもの前や家で全くスマホやタブレットを禁止するというのはパパにとってもストレスです。パパが少しスマホを見たくなったときは、自分時間としてルール化しておく(例:別室に移動する、子どもが寝た後に使うなど)とストレスは減ります。何事もメリハリが大切ですね!
我が家の体験談:ルール導入で激変した日々
最初は「なんでダメなの?」の連続だった
ルール導入初日は「なんで?」の質問攻め。当初親の私たちも戸惑いましたが、声がけ丁寧に続けていくことでなんとかお約束を守れました。その際はたくさん褒め、できるイメージを与えるように意識していました。
2週目には「今日あと何分?」と自分で時間を意識し始めた
子ども自身が時計を見ながら「残り何分?」と自分で時間を管理し始め、驚いたのを覚えています。こう言った意識が芽生えたのも、お約束の上でやりたいことを行うというルーティンが確実に身についてきたからだなと感じます。
1ヶ月後には親子でスマホ・タブレット以外の遊び時間が増大!
この生活を続けていくことで、子ども自身スマホやタブレットに依存しずメリハリをつけて遊びを選ぶようになってきました。決められた時間以外はブロックで遊んだり、絵本を読んだりすることがいつの間にか増え、テレビの時間も同じように管理できるようにもなりました!
まとめ:「ルール+代替」でスマホより素敵な時間を育てよう
ここまでご紹介したように、スマホ・タブレット時間のルール設定+魅力的な代替活動がセットになれば、子どもの意識や生活リズムは自然とバランスが取れるようになります。
子どもにばかりルールを押し付けるのではなく、パパも一緒になってルール化し、実行、振り返りをすることで、家庭の安心感と時間がグッと増えます。
皆さんのご家庭でも、まずは「ルール作り、見える化、代替遊びの3セット」からはじめてみませんか?
このブログ「パパ育LOG」では、働くパパが実践できる育児のヒントを今後もお届けします。

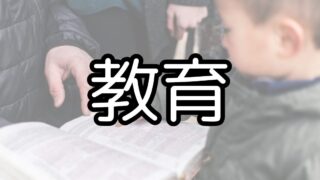
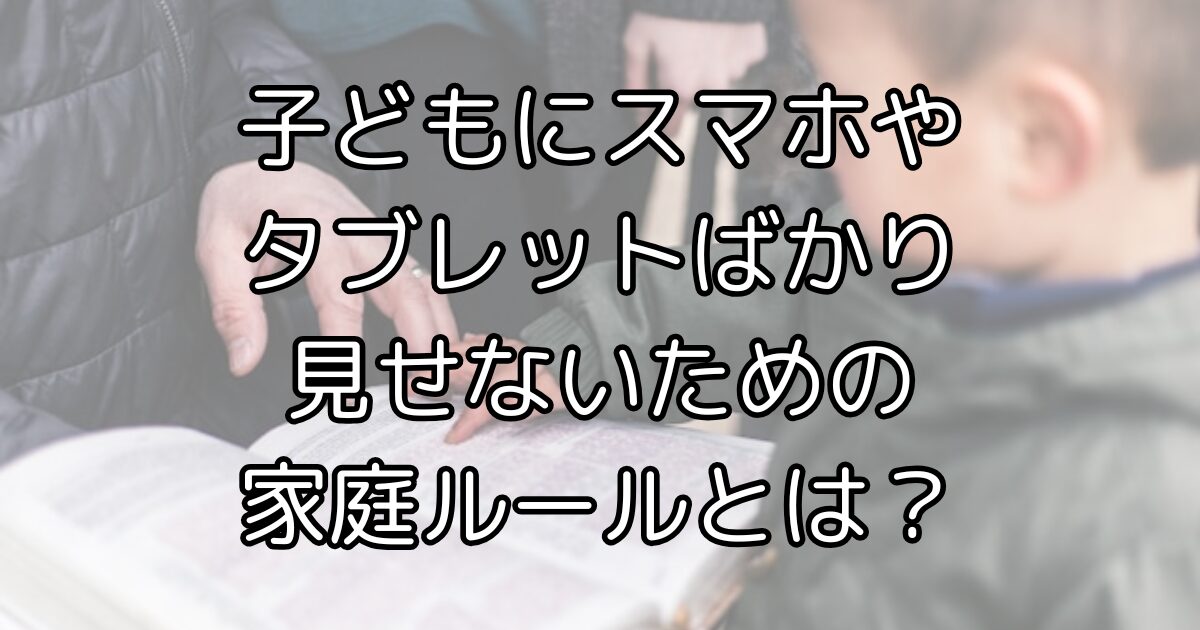
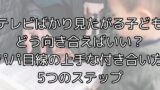
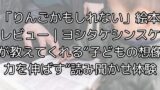
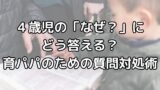


コメント