【結論】夜間育児は“役割の見直し”と“ラクできる工夫”で乗り切れる
共働きで育児中のパパにとって、夜間の赤ちゃん対応は心も体も削られる大仕事。特に生後まもなく訪れる「魔の三週目」。 理由のわからない夜泣きに四苦八苦し、極度の寝不足状態に・・・。寝不足の体に容赦なく迫り来る育児・家事・仕事に追われ、家でも職場でも休まらない日々に「もう限界…」と感じた経験がある人も多いのではないでしょうか? 筆者もその1人です。
この記事では、そんな筆者が実際に試して効果があった“夜間育児のリアルな乗り切り方”を、失敗談と成功体験の両面からお伝えします。
この記事を読めば、共働きでも負担をかけすぎない夜間育児の考え方と、家族と協力して無理なく回す工夫がわかります。ぜひご参考ください!
共働きパパの「夜間育児」がしんどい理由
待望の我が子を育てていく上で、絶対的に避けられない現象が「夜泣き」です。時間やタイミングお構いなく泣き叫ぶ時期は、親の器を試されているかのような心境になりますよね。
特に「魔の三週目」と呼ばれる期間は、永遠とも思える忍耐を問われる育児の試練ですよね。
「魔の三週目」とは、生後3週目頃の赤ちゃんに見られる、急に泣き出したり、抱っこしてもなかなか落ち着かなかったりする現象のことです。これは、赤ちゃんの成長過程で起こる一時的なもので、脳や感覚の発達、ホルモンバランスの変化などが影響していると考えられています。
Geminiより引用
育児経験が2人・3人〜とある方にとっては、「必ず終わりが来るもの」という経験値があるので頑張れますが、第一子でのこの期間は、「いつまで続くのだろうか・・・」という恐怖にも近い不安がつきまといます。筆者も第一子(現4歳の娘)が「魔の三周目」に差し掛かった頃、絶望した記憶があります・・・。
ではなぜ夜間育児がここまで心身ともに負担をかけるしんどさがあるのでしょうか?
① 睡眠が細切れで脳も体も回復しない
ようやく自分の睡眠時間を迎えたのも束の間、我が子の夜泣き発動による対応やオムツ交換、ミルク対応…などなど。2〜3時間おきの対応で睡眠が分断され、睡眠の質がグンと下がってしまい。起きても常に“眠り足りない感”が続き、脳も体も回復している気がしない状況が続きます。
これが一日だけでなく、数日連続で起きることで心身ともに疲労が蓄積していってしまうんです。
② 日中の仕事にも集中できない
寝不足の日々が続いているので日中仕事をする身としては、当然集中力や効率が低下していいパフォーマンスが発揮しにくくなります。会議中にぼーっとしたり、イライラが募ってミスが増えることも。何より辛いのは、そんな家庭の状況は職場や業務には関係なく、心情を汲み取ってもらえないことも負担の一つとなります。家庭と仕事の板挟み状態にストレスも溜まりやすくなり、疲弊度は増すばかりです。
③ 妻との役割バランスで気まずくなる
寝不足で負担がかかっているのはパパである自分だけではありません。当然ママにも同等以上の負荷がかかっており、夫婦共に疲労困憊状態であることもしばしば。寝不足や疲労により気持ちに余裕がなくなり、「俺も疲れてるのに・・・」「私ばっかりやってる・・・」など、つい本音が出てしまうことも。筆者も経験ありますが、夫婦間はお互いの負担が見えづらく、ふとした言動ですれ違いや衝突の原因にもなります。手を取り合って我が子を育てていかなくてはいけないのに、家庭内で気まずくなってしまうことも少なくありません。
【実体験】夜間育児で試してよかった工夫4選
「魔の三周目」を筆頭に、夜泣きなどで夜間育児の負担が増す時期は度々訪れます。そういうものと分かりつつも、やられっぱなしではキツいばかりです。いかに対策を講じて負担を緩和するかがポイントです。
筆者の家で実際に試行錯誤して試して、良かったなと実感した対策や工夫をご紹介します。
1. シフト制で役割分担を明確に
当時の我が家は、娘が夜泣きするたび夫婦2人とも起きて一緒に対応していました。その背景には、妻が夜泣き対応やミルクをやっている手前、自分が寝続けることが申し訳なかったのと、「育児丸投げしてないよ感」をアピールする為という本音もありました。
しかし、「こんな忖度育児をしていては非効率の極みだ・・・」と我に返った筆者は、妻と相談し夜間育児のざっくりしたシフト制を試みました。
具体的には「22時〜2時はパパ、2時〜6時はママ」と言ったように、メインで対応する役割をざっくりとした交代制にしたことで、「今は自分の番じゃないから任せていい」と安心して眠れる時間が確保できました。筆者の仕事の性質上、帰宅が20時〜21時になってしまう生活環境でしたので、こんな感じの時間割で役割分担していました。
2. ミルク準備は“寝ぼけてもできる導線”に
深夜の自分ほど信用できないものはありませんw。寝ぼけながらでも我が子へのミルクをスムーズに対応できるように、事前に哺乳瓶・お湯・粉ミルク・ガーゼ・消毒器を1カ所にまとめて準備しておきます。これで少々寝ぼけていてもミスが減り、娘へのミルクミッションを無事クリアしていきました。
また、先行投資のような形になりますが、哺乳瓶などのミルクグッズは余分に購入しておくのも有効です。あまりの眠さや疲労がひどい時、最悪の場合洗ったり消毒できなくても一晩やり過ごせるよう多めに持っておくのも有りだと思います。後片付けを朝や日中に回せるのは心の余裕としてとても助かります。
3. 赤ちゃんの寝室と自分の寝る場所を分ける
住まいの事情にもよりますが、赤ちゃんと自分の寝る空間そのものを分けるというのもとても有効でした。幸い、当時の我が家はアパートながら一部屋物置化していた部屋があったので、そこを自分の寝室として一定期間仮住まいしていました。
「寝たいときに寝ることに専念できる」という選択肢があるだけで、心理的ストレスが激減したのをよく覚えています。ママの同意も得られるなら、夫婦交代で別部屋で寝る日を作るとお互い効果的です。
4. 便利グッズに頼る
寝不足で追い詰められた時はしのごの言ってられません。いさぎよく便利グッズや道具に頼りましょう!当時の我が家ではこんなアイテムで負担を軽減していました。
- 自動調乳機 … ミルクの温度管理の手間が省けるので、とても重宝していました。
- おくるみ … 原始的ですが、うちの子はおくるみで包むと泣き止むことが多く安定感ありでした。
- 間接照明 … 買っただけで使ってなかった間接照明がまさかの大活躍。程よい暗さにでき寝かしつけには絶妙な空間作りができました。

こんな感じで、物とお金で解決できる負担はどんどん削減していきました。
夜間育児を乗り越える“心の持ち方”
とはいえ、以下に道具や便利グッズで楽を先取りしても、根本のメンタルや心の持ち方はとても重要です。筆者自身、先輩パパさんやママさんにアドバイスをもらって意識するようにした「夜間育児を乗り越える心の持ち方」をご紹介します。
「大変なのは今だけ」と言い聞かせる
「魔の三週目」や「夜間育児」は数週間〜数ヶ月、、もしくは数年で終わるもの。「大変なのは今だけ」当時の筆者はこの言葉だけで、踏ん張るエネルギーが少し湧いてきました。また、夜泣きなどで大変ですが、我が子の成長過程として長い目で見れば一瞬の出来事です。振り返ればいい思い出ですし、我が子との大切な思い出であることは間違いありません。

少々辛くても子どもとのその時しかないかけがえのない時間です。そう考えれば、尊いひとときですよね。
「完璧じゃなくていい」ことを前提に
育児も家事も仕事も、「70〜80点でOK」と思えることも大切です。筆者もそうですが、男性は比較的完璧を求めてしまいがちです。中途半端でやりきれなかったり、自分の思い描く展開にならなかった時、自己嫌悪になったり凹んだりしてしまいがちです。何事も完璧にこなせれば理想的ですが、現実はそんなに甘くありません。完璧を求めれば求めるほど、理想とのギャップに苦しみます。であれば「完璧じゃなくていい」を前提に、「このくらいできてればざっくりOK」的なラインを持っていることで、自分を追い詰めすぎずに済みます。

この考え方に行き着くまでかなり苦労しましたが、今ではすっかり「70点主義者」ですw。
「夫婦で同じ方向を見てるか?」を大事に
パパとママのどちらが大変か。ではなく、「この子を一緒に育てている」という意識を共有するだけで、関係性はグッと良くなります。夫婦とはいえお互い人間で他人様です。互いに敬意を払いつつ、役割や持ち場をしっかりフォローし合い、2人で1チームの意識で我が子と関われれば素敵ですね!
時にはぶつかり、すれ違い、ケンカもします。しかし一番信頼できるパートナーですから、常に同じ方向性を向いているかの意識共有はこまめにとっていけるといいですね。大切なのはパートナーに対する感謝と敬意、そして相互理解です!
まとめ:「魔の三週目」の夜間育児は工夫とチームワークで“なんとかなる”
「魔の三週目」をはじめとした、共働きでの夜間育児は想像以上にハードで親としても試練です。でも、夫婦間の役割を見直し、便利グッズに頼り、夫婦で「気持ちや方向性のすり合わせ」とチームワークがあれば、必ず乗り越えられます。なにより、「魔の三週目」も「夜間育児」の時期も必ず終わりが来ます。
我が子の理不尽夜泣きで寝不足になり、イライラしたり不安になったりする日も必ずあります。でもそれは、パパもママもが頑張っている証拠です。厳しい現実から目を背けず、我が子に対して 「ちゃんと向き合ってる自分、えらい!」と自分を認めてあげてくださいね。世のパパさんはみんな同じ気持ちなはずです!

「魔の三週目」を乗り越えた時、パパとしての経験値と自信は確実に積み上がっていくはずです!パパとしても一緒に成長していきましょう!
このブログ「パパ育LOG」では、共働きパパのリアルな悩みに寄り添う記事をこれからも発信していきます。
次回もぜひチェックしてください!

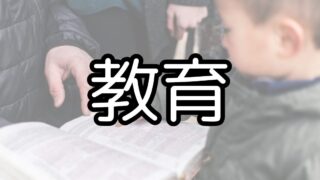

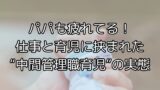
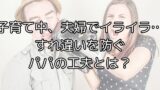
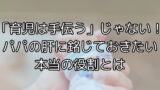


コメント