【結論】完全に禁止しなくても大丈夫!ルールを決めて「テレビとの上手な付き合い方」を教えよう
「子どもがテレビや動画サイトばかり見て困る…」「注意しても全然やめない…」
そんな悩みを抱えているパパさん、多いのではないでしょうか。
でも、ご安心してください。
子どものテレビ好きは“ダメなこと”ではありません。
むしろ、「どう付き合っていくか」「どう時間をコントロールするか」を親の私たちが上手にサポートしてあげれば、子どもにとってプラスに変えることもできます。
この記事では、実際に私自身が我が家で試して効果があった方法や、パパ目線でできる工夫を紹介します。
この記事を読み終わる頃には、「テレビや動画サイトに振り回される毎日」から抜け出せるヒントが見つかるはずです!
なぜ子どもはテレビばかり見たがるのか?
そもそもなぜ子どもはテレビや動画サイトに夢中になってしまうのでしょうか。
我が家でも夫婦で話し合って決めた教育方針の中で、「なるべくテレビ・動画サイトを見せないように育てよう」と取り組んできました。しかし、ワンオペでの育児・家事を進める際や出先でぐずった時などにどうしても頼ってしまうことも何度か。そのほんの数回の機会で、うちの娘もすっかりハマってしまいました。
① 強い視覚刺激で夢中になる
テレビは音も映像もテンポも、子どもにとって刺激的。
特に3〜6歳頃は、動くものや派手な色、音楽に強く反応する時期です。ましてや子ども用の教育番組などの映像は、その性質を逆手に取るように意図的に作られています。
子どもがテレビに夢中になり、もっともっと見たいとなるのはごく自然なことなんです。
② “受け身”で楽しめるから楽
テレビは見るだけでOK。
自分で考えたり動いたりしなくても楽しめるので、疲れているときや退屈なときほど、つい長時間ダラダラと見続けてしまいがちです。
うちの娘も幼稚園から帰った後などにテレビを見ると、疲れと眠気が入り混じる中、口をポカンと開けたまま無心で見ている時があります。
③ 親が忙しいときの「お守り」になっている
各ご家庭において、パパ・ママが家事などで忙しいときテレビをつけっぱなしにして子どもを落ち着かせたり時間を稼ぐパターンが、テレビを利用するタイミングとして一番多いのではないでしょうか。親としてはある程度の時間子どもの気をそらせるありがたいツールなのですが・・・。
それが習慣化すると、子ども自身も「パパママ忙しそう=テレビ」や「ヒマ=テレビ」という思考パターンができてしまいます。
子どものテレビ依存が続くとどうなる?
テレビや動画サイト視聴が100%子どもにとって悪い行いということではないですが、リスクも理解しておきたいところです。
1. 視力低下や運動不足リスク
長時間テレビや動画サイトを見続けると、単純に目が疲れやすくなったり幼少期からの視力低下に繋がることもあります。
また、外遊びの時間が減って運動不足になることも考えられます。子どもにとって身体能力を伸ばす大切な時期に、外で体を動かす時間を減らしてしまうのは考えものですし、ストレス発散の機会も減ってしまいます。
2. 言葉やコミュニケーション能力の発達に影響
テレビや動画視聴は受け身のアクションです。ずっと一方的に受け身で情報を受け続けると、自分で考えて話す力が育ちにくくなることも指摘されています。また、昨今の動画サイトはAIの発達によって視聴者の趣味趣向に合わせた提案をしてきます。子どもの好きな番組やテイストのものを次から次へと提示してくるので延々と見れてしまうし、表現のパターンや言葉に偏りが出てしまうリスクもあります。
一方で、親からはインプットできない違う切り口の語彙力を吸収できるというメリットもあるので、難しいところですが・・・。
3. 家族の会話が減る
「テレビがついてると家族の会話が少なくなる」という声も多いです。
気づけば、家族全員が無言でテレビを見続けていたらもうこんな時間…なんてこともありますよね。やはり家族間の会話やコミュニケーションは、子どもの人格形成を考える上でとても大きい要素だと思いますので、家族会話減少は避けたいところです。
私自身、育った家庭環境がテレビ好きの父親で、食事中もテレビがついていた家庭で育ちました。それだけが理由ではないでしょうが、当時は家族間の会話は少なかったように感じます。その経験則があるので、現在我が家は「食事の時間はテレビやスマホ操作をしない」というお約束のもと過ごしております。
パパができる!テレビとの上手な付き合い方5つのステップ
テレビや動画サイトの視聴に対するリスクも理解しつつ、逆に得られるメリットも活かしていけると理想ですよね。ではどのようにテレビと付き合っていけるといいのでしょうか。
① 親子で“テレビルール”を決める
テレビや動画サイトと付き合っていく上でまず大事なのは、「見る時間」や「番組の内容」にルールを設けることです。
ポイントは、親が一方的に決めないで、子どもと一緒に話し合って決めることです。
例えば…
・「平日は1日30分まで」
・「ご飯中はテレビをつけない」
・「寝る前1時間はテレビ禁止」
こういった具体的なルールが効果的です。
子ども本人も一緒に決めたことですので、意識して守ろうとする流れが生まれます。
さらに、もしこのルールを守れなかったら・・・の場合の決めごともしておけるとより効果的です。我が家では「お約束を守れなかったらおやつが半分になる」と決めています(もちろん子ども本人と一緒に決めました)。今の娘にとって「おやつが減る」という減少は「テレビをもっと見る」よりも比重や価値が大きいので、かなり守るようになりまた。
ちなみにこの「約束が守れなかったら・・・」の考え方は、奥田健次先生の著書『子育てプリンシプル』を読んで参考にした育児方です。行動分析学の専門家であり、テレビでも活躍する臨床心理士の奥田健次先生が、「子育ての原則=プリンシプル」を実例とともにわかりやすく解説した私の育児バイブル的な一冊です。
② 親が“ながら見”をやめる
基本的な姿勢の話になりますが、パパ自身がダラダラテレビやスマホ・タブレットを見ている習慣があると、子どもも「テレビはいつでも見ていいもの」と思ってしまいます。
まずは親が見本を見せることが、一番の近道。私たちの想像以上に、子どもたちは親の姿を見て吸収し育っているものです。
③ 親子で「見る番組」を選ぶ
どうせ見るなら、教育番組や知育アニメ、ドキュメンタリーなど“学びにつながる番組”を選ぶのがおすすめ。
例えばNHKの「ピタゴラスイッチ」や「ダーウィンが来た!」など、親子で楽しめる番組もたくさんあります。
ちなみに我が家ではEテレも見ますが、お気に入りは「ココメロン」です。
ココメロンは、主に未就学児(特に0歳から5歳くらい)を対象とした、英語の童謡や教育コンテンツを提供するYouTubeチャンネルです。アメリカ発で、世界中で人気があります。これを見せる時は音声も字幕も英語のバージョンを選び、少しでも英語のヒアリング力が養えるといいなと願っています。
④ テレビ以外の“楽しい選択肢”を増やす
何か暇を持て余したらテレビを・・・。こんな「テレビ以外にやることがない」状態を減らすことも大切ですね。
例えば…
・絵本を読む
・ブロック遊び
・お絵かき
・外でボール遊び
など、パパが率先して一緒に遊ぶと、自然とテレビから離れる時間が増えます。子ども自身、本音はテレビよりもパパと一緒に何かしたいというのがあると思います。親であるこちらの向き合い方一つで変わるものですね。
⑤ 「テレビを見ること」自体を悪者にしない
テレビや動画サイトをあまりに強く禁止すると、逆に隠れて見ようとしたり執着が強くなることもあります。なんとなくテレビを見ることが悪いことと印象づいていますが、メリットもたくさんあります。
大事なのは「時間を守って、楽しく見る」こと。
テレビや動画サイトを敵にしない関わり方を心がけて、うまく活用していけるといいですね。
我が家で効果があった!リアル体験談
実際に子どものテレビや動画サイト視聴に対して我が家で実践して効果的だった手法をご紹介します。
【実例①】タイマー作戦で成功!
我が家ではキッチンタイマーを使って「30分経ったら終了」と前もって約束を。「タイマーがなったらテレビお終いにしようね」と約束した後でテレビをつけていました。
前提としては先でもご紹介したルールづくりをしている上でのタイマー活用になります。
最初の頃はぐずりましたが、「お約束守れなかったら・・・」のルールのもと毎日続けることで習慣化できました。今ではタイマーを使わなくてもキリのいいところで自分からテレビを消すようにもなりました。この姿にはパパとして感心してうるっときますw。
【実例②】パパとの“夕方散歩”で自然とテレビ離れ
我が家の生活パターン上、娘は夕方になると「テレビ見たい」と言い出します。そんな時は「パパとお散歩いこう!」とか「今日はパパと一緒に絵本読もうか!」と別の遊びに誘導しました。
普段仕事でいないパパと一緒に何かするという時間は娘にとっても嬉しいらしく、結果夕方のテレビタイムがかなり減りました。
テレビ時間を「親子コミュニケーションの時間」に変えるコツ
次にテレビや動画サイトをうまく活用するコツをお伝えします。
1. 一緒にテレビを見る
テレビをつけてほったらかし・・・ではなく、せっかくなら一緒にみて笑ったり、内容について話したりするだけでも、コミュニケーションのきっかけになります。
「このキャラ好きなの?」「これ面白いね」「どんなお話?」など声をかけるだけでOKです。
余談ですが、意外と子ども向け番組を大人がまじめに見ると面白いです。明らかに親世代に向けたネタが自然に仕込まれていることもあり、思わずクスッと笑ってしまうこともありますよ。
2. テレビの後に「感想タイム」
番組を見終わったあと、「今日何が面白かった?」と感想を聞くだけで、子どもの表現力や会話力アップにつながります。この時の質問のポイントとして、Yes・Noで答える質問ではなく自由な言葉を引き出せる質問方がおすすめです。
▪️Yes・Noで答える質問

今日の内容は面白かった?
▪️自由な言葉を引き出せる質問

今日はどこが面白かった?
子どもの言葉を否定しず、どんどん引き出してあげましょう!
3. 番組をきっかけに遊びに発展させる
例えばワンちゃんが出てくる番組やストーリーを見た後に、一緒に図鑑で犬を調べたり、絵を描いたり…。
テレビを「次の遊びにつなげるきっかけ」として活用していけると、子どもがテレビをきっかけに芽生えた好奇心やこ興味をさらに増幅させたり伸ばすことにつながります!
まとめ:「テレビ好き=悪」ではない!パパの関わり次第でプラスにできる
正直、テレビや動画ばかり見たがる子どもにイライラしていた時期、私ににもありました。ひどい時は仕事用のタブレットを引っ張りだしてきて見せろと泣いたり・・・。
でも、「ルールを決めて、親が関わり方を変えるだけで、子どもは自然と変わる」ということを身をもって実感しました。
大事なのは、「禁止」ではなく「上手に付き合う」こと。
パパだからこそできる声かけや工夫で、今日から少しずつテレビ時間をコントロールしていきましょう!
このブログ「パパ育LOG」では、これからも働くパパたちの悩みに寄り添った記事を更新していきます。
次回もぜひお楽しみに!

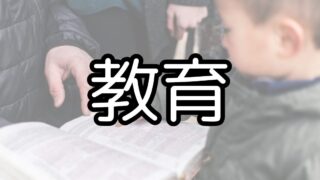
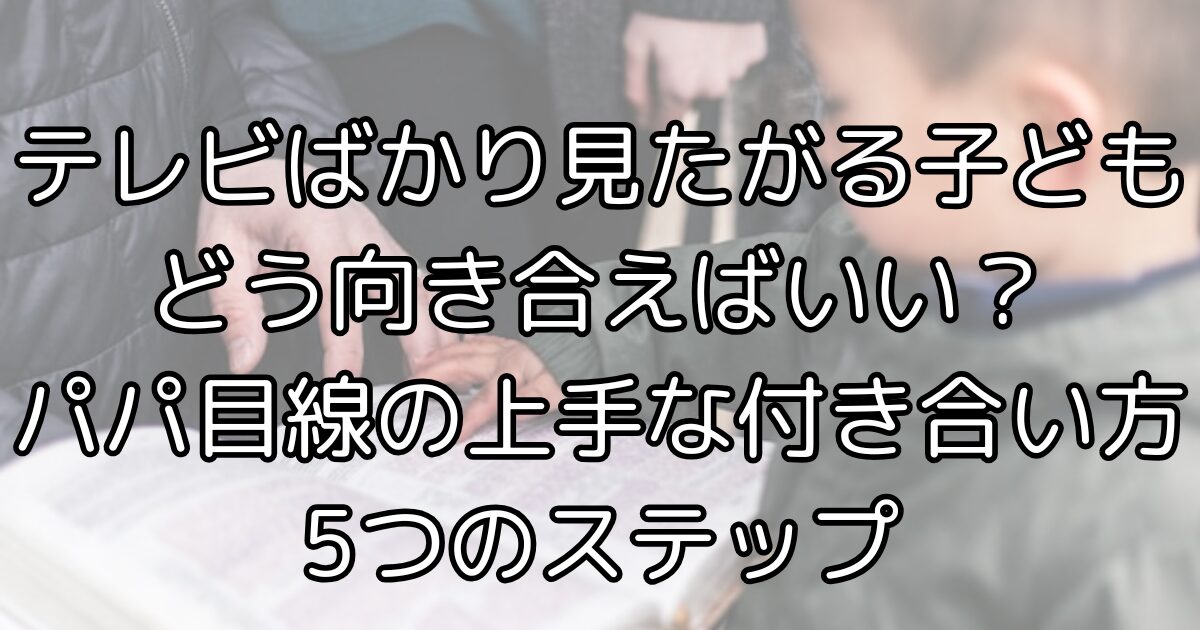
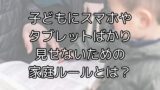
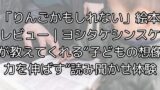
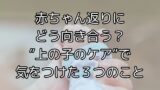

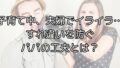
コメント