【結論】上の子の“赤ちゃん返り”は「不安のサイン」|安心できる関わりで乗り越えよう
下の子が生まれて間もなく、上の子が急にワガママになったり、赤ちゃんのような言動をしたり、できていたことをしなくなったり。いわゆる「赤ちゃん返り」。
働き盛りのパパにとっても、赤ちゃん返りの我が子への対応に困る育児悩みの一つですよね。
でもその裏側には、「パパ・ママを取られる不安」や「もっと甘えたい気持ち」があるのです。
この記事では、2児の父である筆者が実際に経験した“赤ちゃん返り対応のリアル”と、上の子との関わりで意識した3つのポイントをご紹介します。
この記事を読めば:
・赤ちゃん返りの原因とサインがわかる
・共働きパパでもできるケアの工夫がわかる
・「上の子にどう接すればいいか」
がわかります。ぜひご参考ください!
赤ちゃん返りとは?上の子が見せる変化
第二子が産まれてから、上の子には具体的にどんな変化が見られるのでしょうか。
よくある赤ちゃん返りの行動
- 急にオムツに戻りたがる
- 赤ちゃんのような言葉遣いをする
- ぐずりやすくなる・癇癪を起こす
- 下の子にちょっかいを出す
などが一般的に起きやすい変化です。筆者の娘(当時3歳)は「指しゃぶりがひどくなった」など、子どもさんによって変化のパターンは様々なようです。
しかし、これらの行動変化は決して「わがまま」や「甘えすぎ」ではなく、親の愛情を再確認したい気持ちの表れ。 「パパ・ママに嫌われたかも」「パパ・ママが下の子にとられた」という不安に対して、試すような行動をしてしまうのです。

私の娘も「トイレに行かなくなる」、「指しゃぶりが悪化する」など、顕著に行動の変化がありました。
我が家で実践した“上の子ケア”で気をつけた3つのこと
赤ちゃん返りの行動変化がでた娘に対し、我が家で実践した“上の子ケア”をご紹介します。
1. 「上の子だけと過ごす時間」を確保する
我が家で実践してみて最も効果を感じたのは、どんなに短時間でも“上の子だけに集中する時間”を持つことです。
我が家では妻が下の子を寝かしつけている時間に、私が上の子とお風呂に入ったり、寝る前の絵本タイムを担当しました。その際意識したのは、なるべくたくさん話をすること。「今日は保育園でどんなことがあった?」「お昼ご飯は何を食べたの?」など、たわいもない話をたくさん問いかけ、娘への関心を全力で見せる努力をしました。
その効果か、「今日はパパを独り占めできた」と思える時間があることで娘の心が安定し、赤ちゃん返りの症状や頻度がぐっと減りました!
2. 「上の子の成長」をちゃんと褒める
赤ちゃん返り中でも、ふと見せるお姉さん・お兄さんらしい一面。下の子にヤキモチ妬いたり嫉妬心はあっても、やはり弟妹が可愛くて面倒を見るシーンも多いはずです。
その瞬間を逃さず、「◯◯できてすごいね!」「さすがお姉ちゃん(お兄ちゃん)だね!ありがとう!」と、成長を認める声かけを意識しました。
特に効果があったのが、あえて他人の前で“上の子のことを褒める”ことです。 祖父母や親戚や友人に「この子、本当に弟のこと大事にしてくれる優しい子なんだよ」と言った瞬間、嬉しそうな顔をしていたのが印象的で今でも覚えています。
3. 下の子を巻き込み「家族の仲間」にする
ついつい上の子に言ってしまいがちな「我慢して」「お姉ちゃんでしょ」といったフレーズ。このような一言は子どもにとって大きなプレッシャーや窮屈さを与えてしまいます。我が家ではプレッシャーをかけるのではなく、“お姉ちゃんって楽しい”と思えるような関わりを意識していました。
例えば、下の子のミルク作りを手伝ってもらったり、「○○ちゃんがやさしくヨシヨシしてくれたから、△△くん泣き止んだね、ありがとう!」と伝えたり。
下の子に関わる行動をする時、親の私たちがやってしまった方が圧倒的に速くて効率的な作業も、あえて上の子にお手伝い頼んでみたり一緒にやってみたり。こういった積み重ねが、本人にとって「パパやママの役に立ってる」「頼られている」という感覚になり、自己肯定感が増したり「お姉ちゃんって楽しい」というマインドに変わっていくのを感じました。
赤ちゃん返り中のNG対応とは?
叱りつける・無理に我慢させる
2人以上のお子様を持つご家庭のあるあるだと思いますが、「お姉ちゃんでしょ」「もう赤ちゃんじゃないでしょ」は典型的なNGワードになります。
子どもは不安や寂しさを我慢しすぎると、かえってストレスや自己肯定感の低下に繋がってしまします。とっさに出てしまう言葉として、筆者自身も何度も後悔と反省をしながら、なるべくこう言ったフレーズを言わない意識をしていました。
完全に“親のサポート役”にしてしまう
上の子を「もう手がかからない存在」として扱いすぎると、本人は逆に「自分は大切にされていない」と感じさせてしまうリスクがあります。「頼りにしているよ」と言った声かけは効果的ですが、上の子もまだまだ甘えたい盛りの「子ども」であることを忘れないようにしましょう。

時には上の子を思いっきり甘えさせてあげる時間を作るのも、とても大切だと思います!
働くパパだからこそできる関わり方
赤ちゃん返りをした上の子に対して、フルで時間やエネルギーを使えないのも働くパパの悩みどころです。そんな働くパパだからこそできる関わり方をご紹介します。
短時間でも「密度の高い関わり」を
特に平日は仕事でなかなか時間が取れないというパパさんも多いはずです。
そんな中でも、家で過ごす時は「スマホを置いて5分だけ集中して遊ぶ」「1冊だけ絵本を読む」など、上の子だけに向ける密度の濃い関わりが大きな安心感に繋がります。
筆者も子どもを寝かしつけるまではスマホやダブレットは触らないと決めてから、こういった時間が改めて貴重だし大切だと実感しました。
「仕事や自分の話」より「子どもの話」を家での最優先に
帰宅後、家族でさまざまな会話が飛び交うかと思います。そんな中でも、上の子の話題を意識的に取り上げて会話を広げましょう。「今日はどんなことをして過ごしたの?」「誰と一緒に遊んだのかな?」など、パパと離れていた時間帯のことをたくさん聞いてあげましょう。
「パパは私のこと気にしていてくれる」「自分に注目が向いている」と感じられるだけで、心が満たされていきます。だんだんこちらから聞かなくても自分から今日の出来事や感じたことを話してくれるようにもなります。どんな内容でも否定せずしっかり聞いてあげましょう!
まとめ:上の子の「心のSOS」に気づくパパでいよう
赤ちゃん返りは、上の子なりの心のSOSです。
「お姉ちゃん(お兄ちゃん)だから」という言葉で片付けず、上の子の不安や寂しさに向き合い「安心できる居場所」をつくってあげることが、何より大切です。
仕事も家庭も両立しなくてはいけないパパにとって、できることは限られているかもしれません。 でも、“自分はパパに愛されている”という実感があれば、上の子の赤ちゃん返りは必ず落ち着いていきます。
上の子との時間を大切にしながら、一緒に家族として成長していきましょう!
本ブログ「パパ育LOG」では、育児中のパパに役立つ等身大でリアルな情報を発信しています。次回もお楽しみに!

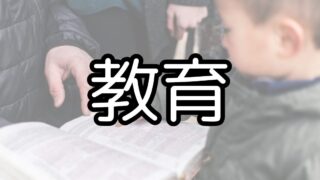
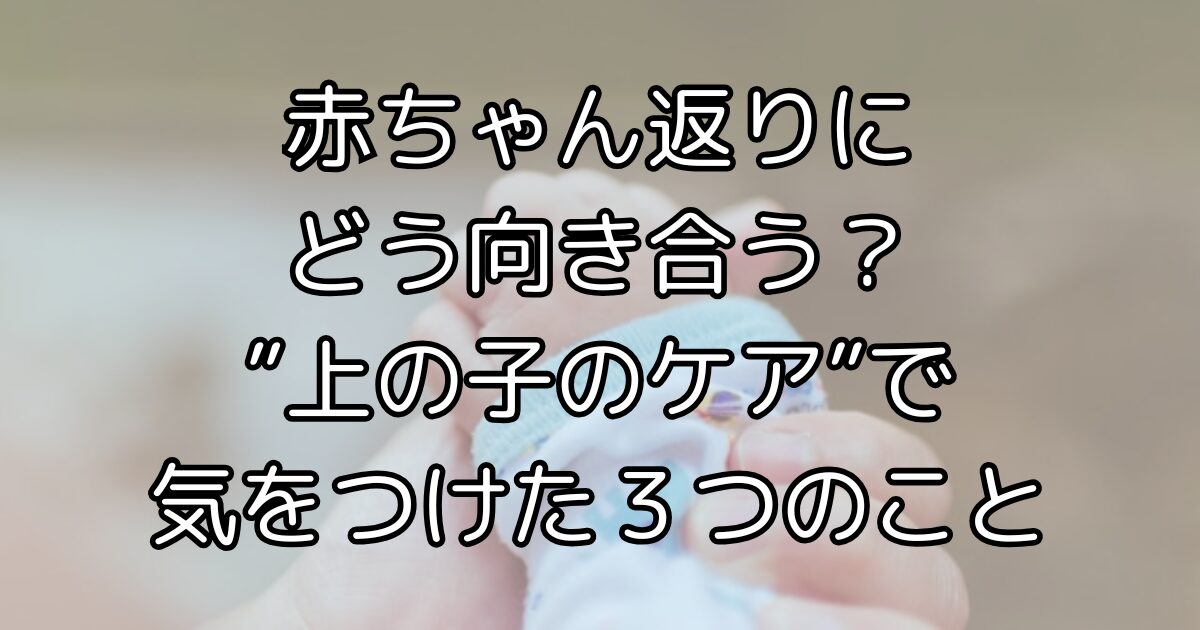
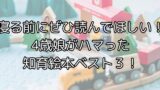

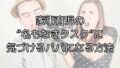

コメント