待望の第一子。我が子の誕生の喜びの裏についてまわる不安を育児経験のないパパさんは感じたことがあるのではないでしょうか?赤ちゃんも0歳なら、初育児のパパさんにとってもパパ0歳児です。「0歳の赤ちゃんって何に気をつけたらいいの?」と不安になるのは当然ですよね。
この記事を読めば、0歳児育児に必要なざっくりとした基礎知識(授乳・寝かしつけ・離乳食・安全・病気のサインなど)がパパ目線で整理され、もしものワンオペでも安心して対応できるようになります。ぜひご参考ください!
0歳育児の大きな特徴:まず知っておきたいこと
育児に向かう前に大切なのは事前準備。そもそも0歳児の赤ちゃんにはどんな特徴や性質があるのでしょうか?そこを事前に認識しておくだけで、向き合い方がかなり変わります。
0歳の育児は基本「食べる(飲む)・寝る・泣く・排泄」の繰り返しです。その中で親としてすべきことはシンプルに以下の3つになります。
①赤ちゃんが安全に過ごせる環境を整える
まずは赤ちゃんが安全に過ごせる環境を用意することが優先事項です。室温や寝る場所の安全性、段差や落差や落下物などが最小限の環境を準備できるとベターです。赤ちゃんは想像以上に環境の変化に敏感です。様々な要素の中でも、やはり親の我々の存在や接し方が最重要かと思います。物質的な不備があっても、パパやママが側で寄り添っているという精神的安心感が大切ですね。
②成長に合わせたケア(授乳、抱っこ、離乳食など)をする
0歳児は日を追うごとに成長変化します。環境次第ではありますが、いつもと同じ対応やケアではフィットしない瞬間が多々おきます。抱っこの仕方や授乳の体勢やミルクの温度など、些細な変化に敏感です。今は何が1番居心地がいいのか、落ち着くのかを探りながら接していくのがおすすめです。

うまくいかず泣き止まない日もありますが、ピタッとハマった時は達成感ありますよ!
また、(特に第一子の時は)一般的な赤ちゃんの成長速度や成長目安と我が子を比べてしまいがちです。平均より成長や発達が遅れると大きな不安を抱いてしまいますが、その子にはその子の成長ペースがあり、ほとんどの場合が問題ないケースが多いです。離乳食の進みが遅い、喃語のパターンが少ないなど、いろんなケースがありますが、まずは焦らせず我が子のペースを尊重してあげましょう。
我が家の娘(4歳)と息子(1歳)を比較すると、息子が圧倒的に成長がゆっくりでした。一般論や傾向はあるものの、それも一つの個性だと考えるのもありだと思います。
③病気や事故を防ぎ、異常や違和感があれば早めに気づく
親として神経を使うポイントに、我が子の体調や身体的な怪我などがあります。0歳の頃はまだまだ人間としての免疫や肉体的強度が少ないので、ちょっとしたことで発熱や吐き戻したり下痢したりします。最初の頃はその都度動揺しますし、心配は尽きませんよね。
良くも悪くも現代はスマホなどから膨大な情報を手に入れることができます。赤ちゃんに何かあった際はその度に調べて対応策を調べられるのも安心材料です。しかし、情報がありずぎることで自過剰な心配材料が増えてしまうことも多々あります。自己判断にはなってしまいますが、情報の取り方も適度にコントロールすることも大切です。ネットや先輩パパやママのアドバイスを聞いた上で、それでも本当に困ったら医療機関等専門家に相談するのが安心ですね。
この基本を押さえておくと、不安がぐっと減ります。
新生児期(0〜3か月)に気をつけること
授乳の基本
授乳にも母乳とミルクと二種類あり、どちらかだけというご家庭もあれば両方を組み合わせているというご家庭もあります。母乳でもミルクでも「赤ちゃんが満足し、体重が増えているか」が大切です。
母乳だけはママにしかできないことですが、パパにできることとしては授乳の準備・哺乳瓶の洗浄や消毒・授乳後のゲップ補助・ミルク授乳などがあり、重きはサポートを意識するとスムーズです。これだけでもママの負担は大幅に減り、夫婦間の連携やコミュニケーションもうまくいきます。
オムツ替えをスムーズにするポイント
- 替える前に必ず新しいオムツとおしりふきを準備
- オムツ替え用に防水シートをひき、赤ちゃんを寝かす
- おしりかぶれ防止のため、水分はしっかり拭き取る
- うんちのときは背中漏れに注意
- オムツを履かせた後はもも部のギャザーをしっかり出してフィットさせる
不慣れなうちはオムツ替えは四苦八苦。オムツ替えにまつわるトラブルやアクシデントは何度かは起きます。慣れないうちは「手順を声に出しながら替える」と落ち着いてできます。

赤ちゃんによりますが、よく動く子には小さめのおもちゃを持たせるとスムーズに行いやすいです!
また、外した使用済みオムツの保管場所も衛生面含め悩ましい問題です。我が家のおすすめは防臭効果も合わせてこちらの「オムツ処理ポット」です!
ゴミ捨ての時にまとめて捨てるのも楽になります!詰め替えカードリッジもあるので、長く愛用できます!
抱っこと寝かしつけ
0歳育児の最大のお悩みごとは、「寝かしつけがうまくいかない、泣き止まない」です。連日の夜泣きね不足が続き、それでも仕事に行き、帰ればまた寝不足のまま育児をする・・・。そんなルーティンで身も心も疲れ果ててる状況で、泣き止まない我が子をあやし続けることは、仕方ないこととはいえかなり忍耐力が問われます。少しでも負担を減らすため、寝かしつけのノウハウはたくさん欲しいところです。
絶対効果がある!とは断言できないものになってしまいますが、筆者の経験上、泣き止まない時の寝かしつけは「環境」と「リズム」がポイントです。
理想の条件として、
- 部屋は暗めに(間接照明があれば○)
- 室温は24~26度くらいを保つ(季節による)
- 赤ちゃんが「く」の字になるような抱き方をする
- 適度な揺れ感と子守唄(鼻歌でも○)

赤ちゃんは立って抱っこすると落ち着きますが、なぜか座ると目を覚ましてしまうことが多いです。少々しんどいですが、深く眠りにつくまで立ち姿勢での抱っこがおすすめです。
適温の暗めの部屋・一定の子守歌・軽いリズムでの抱っこなど、眠りにつきやすい状況を習慣にできると、赤ちゃんも安心して落ち着きます。寝に入るルーティンを構築できるまで根気よく取り組んでいきましょう!
SIDS(乳幼児突然死症候群)予防
我が子に考えたくないことですが、あまり生後間もない赤ちゃんに稀に起きてしまう悲劇の中に、SIDS(乳幼児突然死症候群)というものがあります。
乳幼児突然死症候群(SIDS:Sudden Infant Death Syndrome)」とは、それまですくすく育っていた赤ちゃんが、ある日突然、眠っている間に亡くなってしまう病気です。
赤ちゃんが突然亡くなることは、生まれつきの病気や感染症、窒息事故などによっても起こることがありますが、SIDSはそれらと異なり、何の予兆や既往歴もない赤ちゃんが睡眠中に突然死に至る、原因の不明の病気です。
日本でのSIDSの発生数は減少傾向にあるものの、令和6年(2024年)は51人の乳幼児がSIDSで亡くなっており、1歳未満の赤ちゃんの死亡原因としては第5位(令和6年)となっています。
発症するのは、乳児期の赤ちゃんに多いですが、まれに1歳以上でも発症することがあります。また、多くが寒い時期に発生しています。政府広報オンラインより引用
具体的な対策としては・・・
- うつぶせ寝を避ける
- 顔周りに布団や枕を置かない
- 授乳後すぐは仰向けで寝かせる
などがあります。親である我々が睡眠中に起きることもあるので、完璧に防ぐことは難しいですが、1つでもリスクの芽を積んでおくのもとても重要です。
乳児期前半(4〜6か月)に気をつけること
発達の目安と特徴
生後4〜6ヶ月の赤ちゃんは、首が座ってきて縦抱きができるようになったり、寝返りなどもするようになっち来る時期です。発育が順調な子だとおすわりも短時間なら1人でできるようになります。感情表現が豊かになり、笑ったり「キャーキャー」声を出したりと、大人が見ていても微笑ましい反応をするようになってきます。
行動範囲が少し拡大した赤ちゃんにパパができる事は、「床に布団やマットを敷いて安全に練習できる空間を作る」ことや、「赤ちゃんの伸び伸びとした表現を引き出すよう積極的に関わる事」です。

とにかく可愛いこの時期。笑顔が見たくていつも以上にお世話をしたくなります!
離乳食のスタート
離乳食は目安として生後5〜6か月頃からスタートする時期になります。今までミルクや母乳しか口にしてなかった赤ちゃんが、初めて固形に近いものから食べていく様は、親としても何だか感慨深いですね。どんなものから食べさせるのか?量は?回数は?まずは一般的な知識や基準を知らないと不安に感じることも多いと思います。
“最初は「10倍がゆ」小さじ1から“など、当時筆者が離乳食について参考にしたリンクもぜひご参考ください。
離乳食はついついママ任せになりがちですが、パパも一緒に作れば食育の第一歩になりますし、子どもにとっても食を通してパパとの絆を深めるいい機会になります!
予防接種スケジュール
0歳は予防接種が多くとても複雑です。接種の種類やタイミングなど、よく調べないと把握しきれない程あります。筆者も第一子の時は何が何だかわからなかった記憶があります。
まずはよく調べることが大切です。
種類多くややこしいですが、母子手帳やスマホアプリやカレンダーで管理すると抜け漏れを防ぎやすくなります。
なお、予防接種やワクチンについての価値観は人やご家庭によって様々です。あくまで義務ではありませんので、打つ打たないの判断をするためにメリットデメリットをしっかり調べておくということが大切だと筆者は感じます。
乳児期後半(7〜12か月)に気をつけること
後追いと人見知り
乳児期後半にさしかかると、ママから離れられず泣くことも増えてきます。我が家の子どもたちもまさにその状態でした(特に下の息子)。この時期はパパでは子どもも納得せず精神的にも堪えますが、基本的に一時的なものなので安心してください。ママも子どもが離れず思うようにことが運ばないことが多いので、精神的にも不安定になりやすいです。
そんな時こそ、パパが「抱っこ係」「遊び相手」を積極的に行うと、ママにも心の余裕が生まれます。
また外出先等で家族以外の人への人見知りも顕著になることが多いです。相手への気は使いますが、これも一つの成長過程・社会勉強と考え、なるべく人との関わりの場を設けることが、将来の我が子の対人能力を左右するポイントにも関わってきます。
ハイハイ・つかまり立ち
この時期になると足腰がしっかりしてきて、ハイハイやつかまり立ちをするようになってきます。我が子の成長の中でも見応えと喜びのある1シーンではないでしょうか。今までが基本寝転がったり座って移動しなかった状態から、行動範囲が一気に広がります。それによって新たな心配事も生まれます。
考えられる状況としては、広範囲の床の環境(物の位置や清掃状況など)、転倒した際のリスク、段差や窓などからの転落などなどがあります。ポイントとしてはリスクの先回りで未然に防ぐということ。
- 床に小さなものを置かない(誤飲予防)
- テーブルや柱などの角をカバーする
- 階段・ドアにはベビーゲートやとおせんぼを配置
などが有効です。ホームセンターや子ども用品売り場などにも様々な対策ツールが販売されているので、一度検討してみるのもいいですね。
ただ、あまりに過保護にリスクの芽を取り払ってしまうのも考えものです。子ども自身に体験を通して「危険なもの・こと」を学ばせるというのも重要な教育です。重大なリスクは防ぎつつも、危険なこと危険と認知させるための環境も確保できるのが理想ですね。
全年齢共通で気をつけたいこと
はちみつを与えてはいけない理由
1歳未満にはちみつを食べさせてはいけません。理由としては「乳児ボツリヌス症」を発症する危険があるからです。
乳児ボツリヌス症とは、はちみつに含まれるボツリヌス菌が腸内で増殖し、毒素を産生することで数日間の便秘、哺乳力の低下、泣き声が弱くなる、全身の脱力などがあり、まれに死亡することもあります。ボツリヌス菌は熱に非常に強く、通常の加熱調理では死滅しないため、はちみつ入りの加工品も1歳未満の乳児には与えないようにしなくてはいけません。
一般的に1歳以上になると腸内環境が整うため、はちみつを食べても問題ないとされています。初めて与える際は少量から始め、体調に変化がないか様子を見ることがおすすめです。
厚生労働省も公式に注意喚起しています!

お恥ずかしながら、私も育児を経験するまでは未満児がはちみつを食べてはいけないということを知りませんでした。
夜泣きとの付き合い方
子どもの月齢問わず、夜泣きはいつ何時でも起きることです。育児世代にとって心身ともに大きな負担と悩みになります。パパにできるのはとにかくママの負担を減らすこと。夜の抱っこを率先してやったり、時間を区切って役割を分担したり。
月齢によって授乳なども絡むため、いろいろ簡単ではありませんが、家族の相互理解と協力があれば安心して乗り越えられます!
発熱や体調不良の見極め
未満児は免疫がまだまだ発展途上なので、様々な体調不良が起きます。逆にいうと、症状が出た数だけそれに対する免疫や抵抗力を獲得していくので、強く育つためには喜ばしい現象といえます。とはいえ苦しむ我が子を手放しで放って置けないのも親の心情です。まずは子どもの様子や変化・症状をしっかり見て経過を追うことも大切です。いつからなのか、症状はどんな経過かなど、状況を認識しておくことでその後の対処も変わってきます。特に、
- 40℃以上の発熱が数日続く
- 水分を取らない・ぐったりしている
- 呼吸が苦しそう
など、突発的な物も含め症状が重い場合は迷わず小児科などの医療機関へ相談しましょう。頼れるかかりつけ医が決まっていると、なお安心ですね。
ワンオペパパ目線の経験談
私自身、妻の外出や入院で当時0歳の娘とワンオペ育児を経験しました。この経験を通じて一番感じたのは、「ママいつもこれをやってるんだ・・・」という妻への尊敬と感謝です。普段外で仕事している間も、ママは子どもと付きっきりで休みなく対応しているんだという「わかってるつもりだけどわかってなかった」部分に触れられたのはとても良かったです。
いざワンオペ育児が始まれば、最初は「泣きやませられない」「寝不足でイライラ」と壁だらけでしたが、先輩パパさんから聞いた以下の対策でかなり救われました。
- 事前に授乳やオムツ替えの動線を日数分準備した
- 便利グッズ(離乳食パック、家電のタイマー機能など)を使った
- 「完璧にやろう」とせず6〜7割でOKと割り切った
結果的に、パパとしての自信がつき、娘との距離も近くなりました。
まとめ:0歳育児はパパの関わりで楽になる
0歳の育児は綺麗事抜きに本当に大変です。ましてや初めての育児経験となれば尚更で、毎日が我が子とという未知との遭遇です。でも、知識と準備があれば不安は減らすことはできます!
ポイントは「赤ちゃんの安全」「成長に合わせた対応」「ママのサポート」。
パパが一歩踏み出せば、育児は「負担」から「家族みんなの成長体験」に変わります!
筆者もまだまだ未熟なパパですが、一緒に成長していきましょう!
当サイト「パパ育LOG」では、働くパパさんに向けた育児にまつわる情報を発信しています。少しでも同じような悩みや不安を持つパパさんのお役に立てれば幸いです!

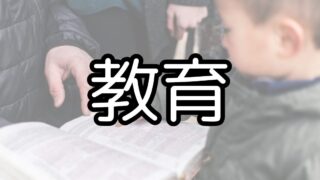
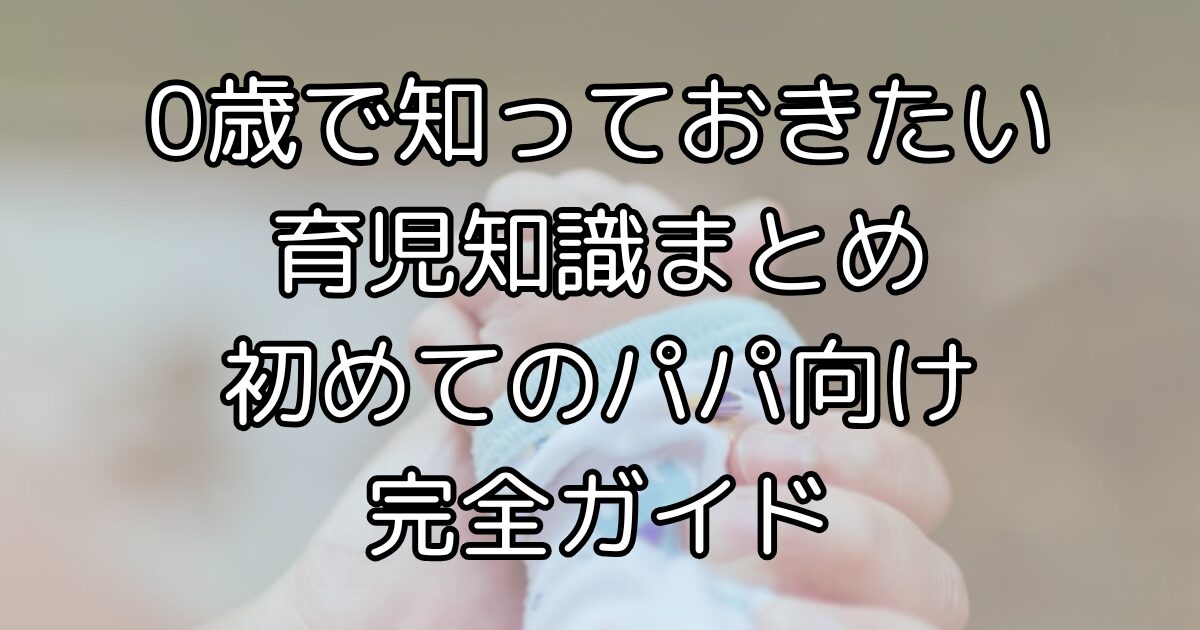

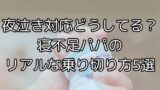
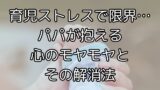


コメント