はじめに:「厳しくしないとダメ?」と悩むパパへ
「このまま甘やかしていて将来大丈夫?」「やっぱり怒らないと伝わらない?」──そんなふうに悩んだ経験はないでしょうか? 特に4歳前後の子どもは自己主張が強くなり、親としてもしつけの方向性に迷いやすい時期ですよね。私自身、娘に嫌われたくない一心で、ついつい甘くなってしまう瞬間が多々あります。その度に自問自答するように悩む日々を送っております。 この記事では、30〜40代の働くパパに向けて、「怒らない教育」とは何か、どのように実践できるのかを具体的にお伝えします。
この記事でわかること
- しつけと怒ることの違い
- 怒らずに伝える具体的な方法
- 怒らない教育がもたらす子どもの変化
- 仕事と育児を両立するパパでも実践できる工夫
「しつけ=怒る」ではない!
怒ることの目的を見直す
そもそも怒ってしまうのは、「ダメなことをやめさせたい」「正してあげたい」という想いからのことが大半のはず。我が子を思うがこそ感情的にもなってしまいがち・・・。しかし、怒ることで子どもが感じるのは“恐怖”や“混乱”であって、行動を見直すきっかけにはなりにくいのです。我が家の娘(4歳)も怒って伝えたり教えたことは、繰り返し同じことをして怒られるというパターンが多かったのです。
「しつけ」とは“教え育てる”こと
本来のしつけの意味は「繰り返し教え、習慣として身につけさせる」ことなんだそうです。つまり怒鳴ったり強く叱ったりする必要はなく、伝え方を工夫して効果的に子どもたちに身につけさせることが大切なんです。この観点で自身の子どもたちへしつけを振り返ると、感情的になってしまって怒ってしまいがちだったなと痛感します。まだまだ未熟ですよね・・・。
では怒らずに伝えるしつけにはどんな効果が期待できるのでしょうか?
怒らない教育が育てる3つの力
1. 自分で考える力
事あるごとに頭ごなしに怒られると、子どもはその状況に萎縮してしまい、「なぜダメなのか」を考えなくなります。怒られている時間がいかに早く終わるかなどを考えてしまい、親が伝えたいことの論点がずれてしまいがちです。
一方、指摘されている状況や理由を丁寧に説明された子どもは、「どうしたらよかったか」を自分で考えるようになります。この経験が積み重なると、「何を改善したら怒られないようになるか」や「褒めてもらえるか」といった一歩先の思考になる習慣がつきます。
2. 感情をコントロールする力
親が感情的に怒ると、子どもも感情的に返します。逆に、落ち着いて対応すれば、子どももその対応を真似て学び習得していきます。親の口癖や所作を真似ていくように、物事に対する対応力やパターンをどんどんインプットしていきます。良くも悪くも親の言動が子どもの模範になっています。こう考えると、自分自身の言動がどうなのかと心配になりますよね・・・。親が感情をコントロールしている姿を見せることができていれば、子どもも自然体でコントロールを習得していくものです。
3. 親への信頼・安心感
怒鳴られ続けると、親に対して「怖い存在」や「逆らえない存在」と思ってしまうことも。また、子ども自身が自己肯定感を無くしていきます。逆に怒らない教育は、子どもとの信頼関係を深め、自己肯定感を育てていきます。時に演出として「怒る」という感情を表現する機会も大切ですが、基本スタンスは「怒る」より「どう伝え理解してもらうか」を冷静に見極めつつ問いかけていくことが理想的ですね。
怒らずにしつけるパパの対応術
1. まずは落ち着く「3秒ルール」
イラッとした時、すぐに怒るのではなく「3秒だけ間をおく」と、冷静に言葉を選べるようになります。このノウハウは、アンガーマネージメントという対人能力のスキルの一つです。本来は「6秒間を置く」というノウハウですが、対子どもの時はスピード感も必要です。それでも3秒グッと堪えてから注意することや指摘することを伝えることで、感情的な言葉やテンションがかなりセーブされます。
アンガーマネジメントにおける「6秒ルール」とは、怒りを感じたときに、衝動的な行動を抑えるために、6秒間待つという方法です。この6秒間は、怒りの感情がピークに達する時間とされており、この時間をやり過ごすことで、冷静さを取り戻し、より適切な対応ができるようになるとされています。
Geminiより引用
2. 子どもの気持ちを言語化してあげる
ことが起きた際に、子ども自身がなぜそうなったのかの背景に目を向けるのも大切です。「こうやって遊びたかったんだよね」「自分でやりたかったんだよね」と子どもの本音を察した上で共感すると、子どもは気持ちが整理され、素直になりやすくなります。
このアクションは実際とても有効で、私も娘に対して意識的に行います。その後の問いかけや指導に対しても納得性を深める要因になってきますよ!
3. NG行動の“理由”を肯定的に説明する
ついついとっさに出てしまう「ダメフレーズ」。育児において親御さんが必ずといっていいほど向き合うことになるであろう「ダメ」というワード。「ダメ」の数だけ子どもの将来の可能性を潰していく・・・といった注意喚起も各所で叫ばれていますよね。
ふさわしくない場面で走り出す我が子にかける言葉として、「走っちゃダメ!」ではなく「ここで走ると人にぶつかって危ないよ」と理由を伝えると、納得しやすくなります。ポイントはいかに「ダメ」という否定的なワードを肯定的に言い換えるか。さらにその行動をすることでどんな結果が起こるかを分かりやすく端的に伝えられるのが理想ですね。
この言い換えのノウハウについては、保育園や幼稚園の先生の言い回しに尊敬の念を持っています。娘の通う園の先生は、「走っちゃダメ!」ではなく「ここは歩こうね」だったり、「歩いている〇〇ちゃんの方が素敵だな」「歩いていく方がみんな嬉しいよ?」というように、多彩な言い回しのパターンで子どもたちに肯定的に伝えています。そのシーンを見るたびに尊敬の眼差しです!
瞬間的に言い回しを変換するのは簡単ではないですが、意識して言い方を考えて向き合うことで少しずつ自然になってきます。
4. 代替案を一緒に考える
親にとってやめてほしいことに対し、「テレビは今は消そうね。でも、あとで一緒に絵本読むのはどう?」など、次の行動の選択肢を提示してあげることで、子どもも納得しやすくなります。ポイントは以下に子どもの意識や興味を惹きつける選択肢を提案できるか。
そもそも本人が興味関心のないことを提示しても、目先のやりたいや楽しいことに没頭しようとします。日頃からどんなことにハマっていて、興味を感じだしているかなどを気に留める観察眼も問われます。
我が家のケースだと、私が基本仕事で帰りも遅くなりやすく、子供と接する時間が圧倒的に妻より少ないです。なので妻に今の様子や関心の矛先がどうなっているのかを共有して情報のアップデートをするようにしています。
それでもコロコロ変わる我が子の興味関心に、的外れな提案して失敗することも多々ありますが・・・w。
仕事が忙しいパパでもできる実践ポイント
朝と夜にだけ“関わるスイッチ”を入れる
私だけでなく、育児に関わるほとんどのパパさんが仕事もしながら育児と向き合っていると思います。ですから、全部の時間を完璧に関わろうとするのではなく、的を絞った時間帯だけはしっかり関わる時間を確保するというのも有効です。例えば「朝食の時間」と「寝かしつけ」といった感じ。自分の決めたタイミングを“子どもとじっくり向き合う時間”に決めておくと、パパ自身の気持ちにもメリハリがつきますし継続しやすいです。
私の経験上、ルーティン化するまでは大変な時期もありますが、子どもにとってもパパと定期的に関われるいいリズムになっていきます。1日に何回もというのが難しければ、一回でも大丈夫です!まずはやってみましょう!
失敗したときは「あとからリカバリー」
どんなに予備知識をつけて準備していても、時には感情的に怒ってしまう時も・・・。
私もそんな時は「やらかした・・・」と自己嫌悪に陥る時もありますが、落ち込んでいるぐらいなら次に繋がるアクションも大切です。
「さっきはあんな言い方してごめんね」と素直に謝ったり、なぜ叱ったのかを優しく振り返りながら伝えることで、子どもとの関係はむしろ深まります。子どもに対しても敬意を持って接するというのも大切なことだと思います。
「しつけは夫婦で価値観をすり合わせる」
どのご家庭でもあるある的に置きがちなのが、パパとママで対応が違うこと。パパにはいいって言われたのに、ママには怒られた・・・というようにパパママで方向性の食い違いがでると子どもが混乱します。
夫婦とはいえ生まれも育ちも違う他人様なので、全てを完璧に擦り合わせることは難しいですが、おおおまかな教育や育児方針の方向性を合わせておくのも必要です。時間が合うときに「こういう時どうする?」を相談しておくことがポイントです。たくさん話し合えるなら、さまざまな事例やパターンを想像して「こんな時はこういう対応」というように決めていけると理想的ですね!
怒らないことで子どもはどう変わる?
自分から謝れるようになる
親から感情的に怒られないという経験が積み重なることで、子どもは「自分が悪いことをした」と冷静に振り返りやすくなります。自覚を持つようなシーンが増えるので、結果的に自分から「ごめんなさい」が言えるようになります。素直に謝れる人(子ども大人限らず)って、本当に素晴らしいと思います。
余談ですが、先輩ママさんから聞いたエピソードで印象的だったものをご紹介します。
ある日、夫婦喧嘩をしているところを息子さん(当時5歳の幼稚園児)に見られてしまいました。その時息子さんは不安そうな顔涙を浮かべ、別の部屋に逃げるように立ち去ってしまいました。
この状況が良くないなと感じたその夫婦は、あえて息子さんの前でお互いが誤り仲直りする様を見せました。仲直りするパパママを見た息子さんは、笑顔になりいつもの状態に戻りました。
数日後、お家に遊びに来ていた息子さんの友人A君と、おもちゃの取り合いで喧嘩になりました。険悪な空気になりかけたその時、息子さんが自分からお友達に謝り、仲直りをしました。
先輩ママさんのエピソードより抜粋
夫婦喧嘩の仲直りをあえて息子さんに見せることで、仲直りの仕方や人としての大切な心を教える印象的なお話でした。親として背中で見せていくというその方流のしつけに、すごく素敵だなって思わされました!きっと息子さんも将来素敵な人になるんだろうなって感じます。皆さんはこのエピソードを聞いてどう感じたでしょうか?
親と“会話”がしやすくなる
大人の私たちでも怒られるのが大好きという人は少ないかと思います。怒られた後はなんだか口数も減りますし、気分も上がりにくくなるものです。子どもであればなおさらではないでしょうか。
怒られると黙ってしまう子も、怒られない環境では「どうしたらいいか」というような次に繋がる考えを自分の言葉で話そうとします。子どもののびのびした自由な発想や日常の会話の質が上がるのも、怒らない教育の効果として期待できますね。
まとめ:「怒らない」=「甘やかす」ではない
「子どものしつけ」を考えれば考えるほど、もっと厳しさが必要なのでは?と思ったり、感情が前に出てつい怒ってしまうものです。怒らずに本質をしっかり伝えられるのなら、ぜひ怒らない教育をしていきたいものです。
怒らない教育とは、決して“なんでも許す”育て方ではありません。ルールやマナーを「丁寧に教える」「親子で一緒に考える」ことで、子どもは自分で判断する力を育んでいきます。
我々 パパの関わり方ひとつで、子どもとの関係は変わります。もちろん厳しさも時に大切ですが、伝え方の工夫が鍵になるんですね!
私もまだまだ未熟なパパ4年生です。皆さんと一緒に成長していきたいと思います!

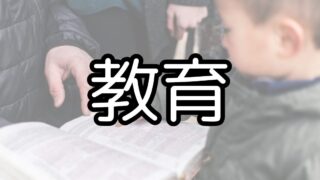
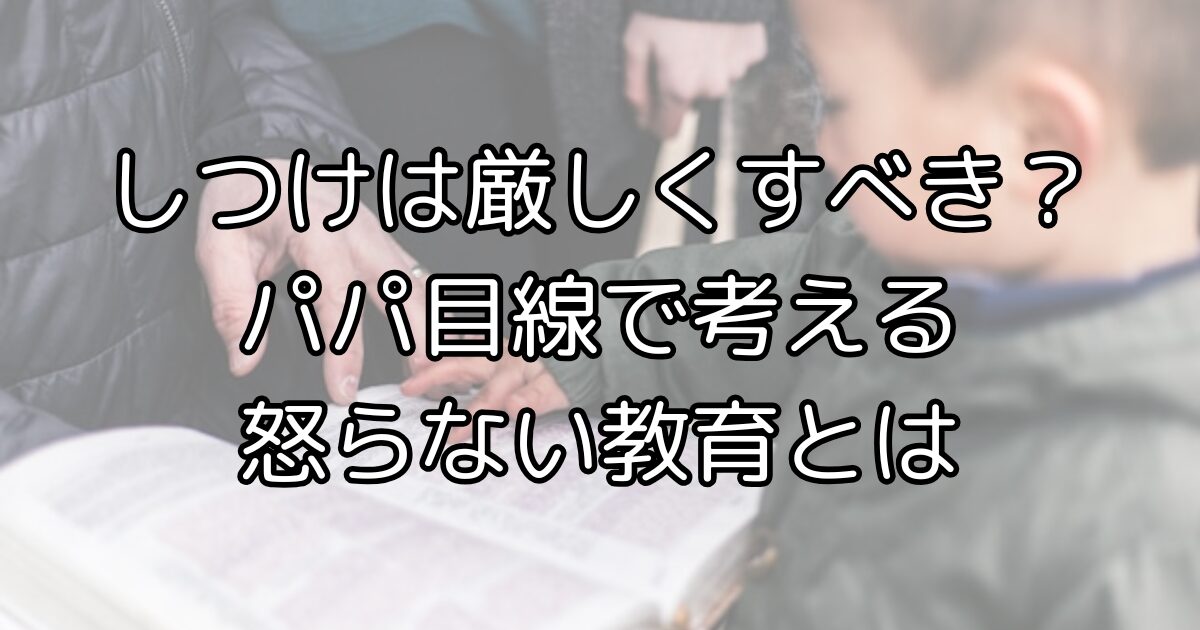
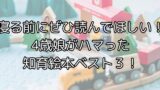
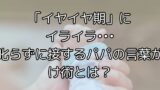
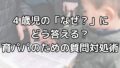

コメント