待望の我が子の誕生、それと同時に始まる激動の育児ライフ。昔と違ってパパも積極的に育児をしていく現代の育児環境において、パパの育休の認知が広がってきました。大手企業だけでなく、中小零細企業でもパパの育休取得を推奨する流れも起きており、より育児に注力しやすい時代性になってきたかと思います。
しかし実情はどうかというと、「うちの会社はほんとに育休取れるのだろうか?」「連日休んで同僚たちがどう思うだろうか・・・」「休んでる期間の収入はどうなるの?」など、少し不安や懸念を抱くパパさんも多いかと思います。
結論から言うと、パパも育休はちゃんと取れるし、収入も国の制度でカバーされるので心配しすぎる必要はありません。むしろ取得することで「パートナーのワンオペ育児による負荷の解消」「家族の絆の強化」「自分のキャリアの幅の広がり」につながります。
この記事では、30〜40代の働き盛りパパに向けて、育休の種類や仕組み・取得の仕方・メリットデメリットをわかりやすく解説します。

私自身が育休を取得した体験も交え、悩んでいるパパさんに「一歩踏み出すヒント」をお届けします。
この記事でわかること
- パパが育休を取得できる仕組みと条件
- シンプルな取得の流れ
- リアルな育休のメリットとデメリット
- 筆者自身の体験談から見えたこと
- 育休取得に悩むパパさんへの具体的なアドバイス
パパの育休の仕組みをシンプルに解説
育休にも種類がある?
そもそも育休と一言に言っても、耳にする育休にも種類があります。
パパに関連する育休には、主に「育児休業」と「産後パパ育休」とあります。
「産後パパ育休」と「育休休業」の大きな違いは、取得期間の時期と柔軟性、休業中の就業の可否、そして申出期限の長さです。産後パパ育休は子どもの出生後8週間以内に最大4週間の取得が可能な制度で、育児休業中に就業も可能です。一方、育休は子どもが1歳(最長2歳)になるまで取得でき、原則として休業中の就業はできないものとなります。
どれくらいの期間取得できるのか?
それぞれの育休がどれくらいの期間取得できるのでしょうか?
- 通常の育休:子どもが1歳になるまで(延長で最長2歳まで)
- 産後パパ育休(出生時育児休業):生後8週間以内に最大4週間
この2つを組み合わせることも可能で、その場合は思った以上に柔軟に取得することができます。
収入はどうなる?
家族の生活を経済的にも守るパパにとって、育休中の収入は大きなポイントになるかと思います。育休期間中につおいては、育児休業給付金が支給されます。
- 最初の6カ月:休業前賃金の67%
- それ以降:休業前賃金の50%
さらに社会保険料が免除されるため、実際の手取り減は2〜3割程度となります。思ったより育休前の生活と比較しても生活への影響は想像より小さくなります。

こうみると改めてありがたいシステムですね!
さらに詳しい制度の違いは、こちらのリンクサイトをご参考ください!私ミカンも育休取得前に参考にしたサイトです!
パパ育休の取得方法(シンプル手順)
パパが育休を取得するまでの、リアルな流れや手順をまとめました。
実際の流れ
- 上司・人事に「育休を取りたい意向」を伝え相談
- 会社に申請書を提出(会社がハローワークへ届け出)
- 育休開始(スケジュールは事前に調整)
- 給付金の申請(会社が代行するケースが多いが、会社と事前に相談して明確にする)
ほとんどは場合は会社経由・主導で進むことが多いため、パパ本人が役所などに駆け回る必要はほとんどありません。とにかく大切な一歩は、「会社(上司)によく相談すること」が重要です。
育休を取るメリットとデメリット
パパが育休を取得するにあたって、時代性に伴い考えられるメリット・デメリットが以下のようにありえます。
メリット
- ママのワンオペ状態の負担を大きく解消できる
- 子どもとの時間が増え、育児スキルが身につく
- 夫婦・家族の信頼関係が深まる
- 社会保険料免除や給付金で経済的負担が軽減される
デメリット
- 給付金等があるとはいえ、相対的に収入が一時的に減る
- 職場に迷惑をかけると感じることがある、気を遣う
- 復職後、仕事の現場感や業務状況の変化への適応が必要になる
このようなメリット・デメリットが考えられます。ただし、デメリットに関しては、「事前準備と工夫」で最小化することができます。
例えば、家計シミュレーションをしておく、職場にて事前に業務引き継ぎをする、復職後は柔軟な働き方を上司・会社に相談するなどです。
同僚に気を遣うというのはいたしかたないことですが、このご時世ですからある種割り切るという発想も大切です。仕事が全てではなく、家族や家庭ありきで自分が仕事できるという前提を大切にしたいものです。
私が産後パパ育休を選択した実際の体験談
私は第一子誕生時はこれらの育休を取得しませんでしたが、第二子誕生時は家庭や身内の状況的に育休取得を検討せざるをえない環境でした。当時の自身の仕事の立場や状況、そして家庭の状況を踏まえて考えに考えた結果、「産後パパ育休」を取得することに決めました。
背景として職場の状況的に長期の休暇が難しかったこと、第一子(当時3歳の娘)の保育園事情などが決め手でした。職場と相談を重ねた結果、第二子誕生時に8日間の産後パパ育休を取得しました。
当初は事前にいろいろ調べてはいましたが、なんだかんだ「収入が減るのでは?」「職場に迷惑をかけるのでは?」という不安でいっぱいでした。
実際に産後パパ育休を取ってみて感じたこと
いろいろな期待と不安を抱きながら育休に突入しましたが、その時感じたのが
- 妻と第二子が産院を退院するまで、家をしっかり守れた
- 退院までの期間、第一子との関わり方がかなり深くなった
- 赤ちゃんのお世話を一緒にできることで夫婦の絆が深まった
- 夜泣きや授乳の大変さをより実感し、ママへの感謝が増した
- オムツ替えや家事を日常的にできるようになり、復職後も自然に育児参加できた
このような点を大きく感じました。
不安だった収入面も、給付金と保険料免除で生活はなんとかなりました。むしろ仕事との兼ね合いがつくのなら「もっと長く取ればよかった」と思ったくらい、自身にとってはいい期間となりました。
育休取得に悩むパパへのアドバイス
お仕事や職場・同僚に対して責任感や使命感のある方ほど、育休取得の検討はより悩ましく感じるかと思います。もし「取りたいけど迷っている」なら、以下を意識すると一歩踏み出しやすくなります。
- まずは夫婦で話す:家計・役割分担・家族の将来設計を共有
- 会社に早めに相談:引き継ぎ準備をすれば迷惑を最小化できる
- 短期間でもOK:1〜2週間の育休でも効果大
- 周囲に体験談を聞く:同じような境遇の先輩パパさんがいれば、不安が具体的に整理される
育休は「取るか取らないか」ではなく、「どう取るか」が大事です。期間が短くても、子どもと過ごす濃い時間は一生の宝物になります。我が子との「その時」は、間違いなく「その時」しかないからです。
よくある不安とその答え
過去に同じような境遇のパパさんに聞かれた質問や不安要素には、筆者ならこう考えます。
Q. 出世に響くのでは?
最近は「育休を取れる人材=信頼されている」と評価されることも増えています。また、社員のパパの育休取得させたという実績のある会社は、社会的にも働きやすい環境というイメージを確立でき、求人効果も高まるため会社にもメリットが高まります。会社の制度や風土・雰囲気にもよりますが、必ずしもマイナスではないと感じます。
Q. 育休中に副業はできる?
結論として一定条件下で可能ですが、収入が増えると給付金が減額される可能性があります。事前にハローワークへ確認しましょう。また、お勤めの会社がそもそも副業可能かを確認する必要があります。
Q. 自営業やフリーランスは?
自営業やフリーランスの方はに関しては雇用保険の給付は受けられませんが、国民年金や国民健康保険の免除・減額制度を活用できる場合があります。こちらもいろいろなケースが想定されますので、ご自身の市町村役場で確認されることをお勧めいたします。
まとめ:育休は「家族への投資」
パパの育休は、単に「休む」ことではなく、いわば「家族と未来への投資」です。収入や職場の不安はありますが、国の制度で手厚くサポートされますし、事前準備で大半を解決することができます。
育休を取ることで、妻のワンオペ育児を減らし、夫婦の絆を深め、子どもとの時間を大切にすることができます。30〜40代の働き盛りだからこそ、今一度「家族の時間」を見直してみませんか?

育休はパパにとっても取得可能で、むしろ取るべき制度。悩む時間より、家族と過ごす時間を優先しましょう。

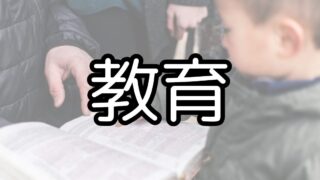
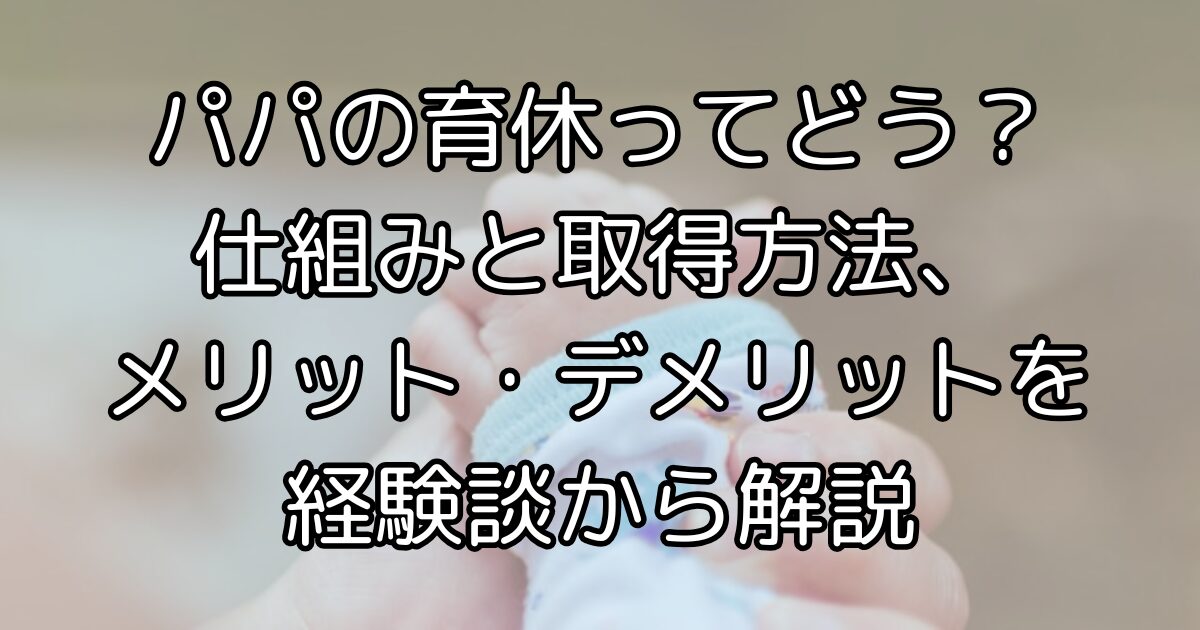

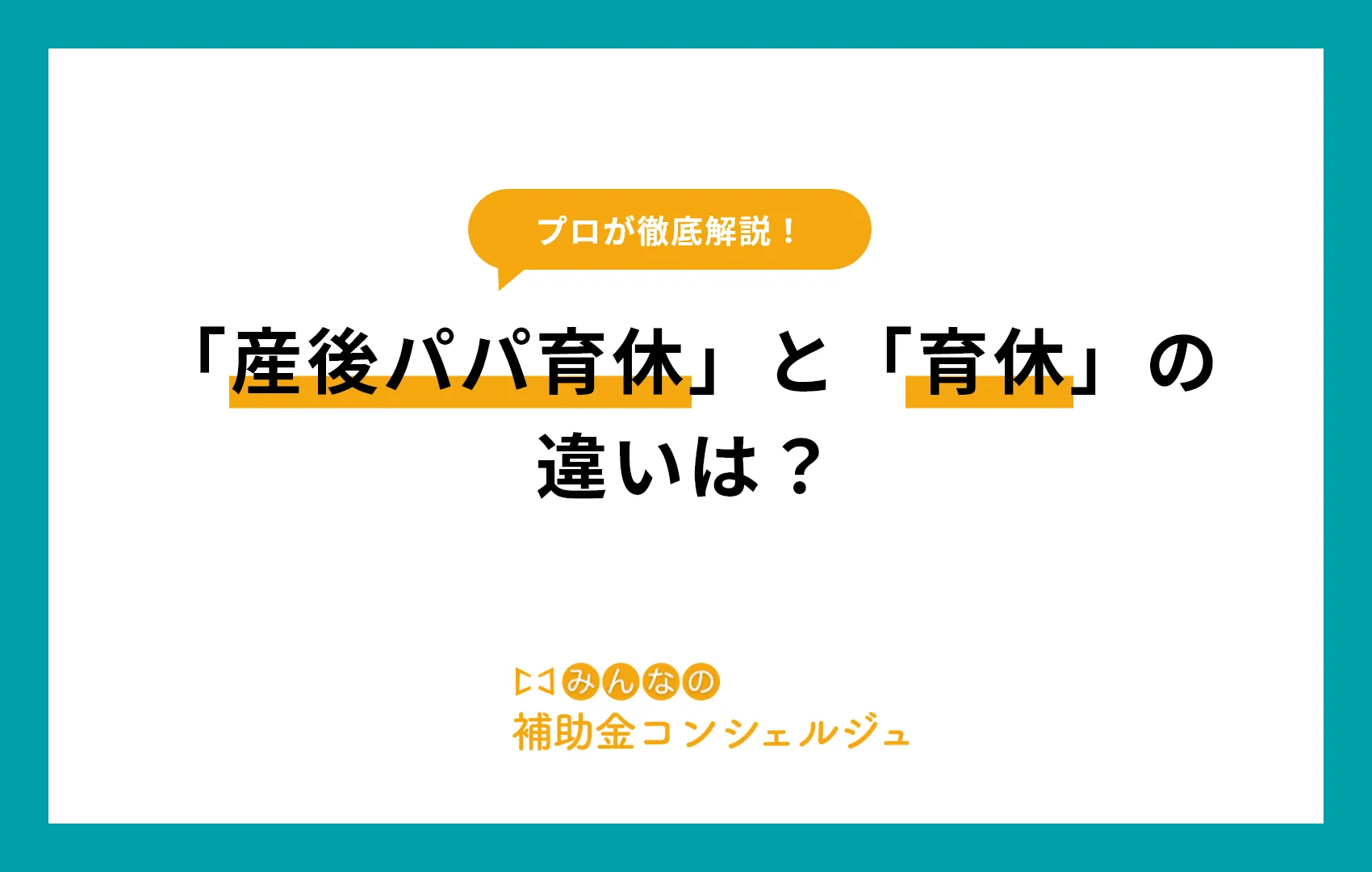
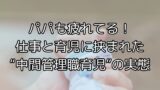
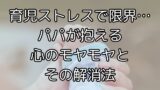


コメント